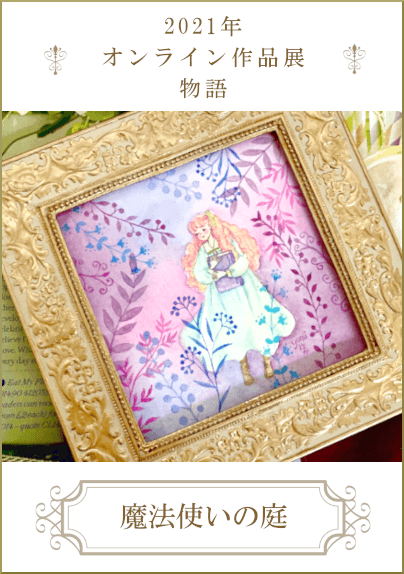
1.魔法使いの悩み
「ママ、この花も摘んでいいの?」
「ああ、それはダメよ、危なかったわ。それは、満月の日に摘むと決まっているのよ。」
美しい春の午後、母と娘が優しい低木の生い茂る丘の 少し開けた小さな庭でうずくまって作業をしていました。あたりは春のたくさんの命の粒を含んだ、湿った甘い香りが漂っていました。
娘は少し躊躇して、それでも母に言いました。
「でもママ、明日の満月は雨なんでしょう?この花は花粉が大事なのに、満月を待ったら花粉が台無しになるわ。
今日じゃダメなの?」
「ええ、そうね、その通りよ。ええと、その場合は・・・」
母は、庭のベンチの大事そうにクッションに置かれた分厚い大きな本を綺麗なタオルで手を拭いたあと、そっと自信なさげに持ち上げてページをめくりました。この大きな本は『ルーファンの書』。この世界では一番信用と権威のある魔法の大辞典です。ルーファンの書は第1巻から第6巻まであり、母が今開いているのは第3巻の植物編でした。
「えーと、マータルの花の花粉の収穫について…」
娘のキトは、母が調べ物をしている間、先ほどまで摘んでいた黄色い蜂蜜色の美しいカヤの草の芽を平らなカゴの上に広げました。この芽は明日の満月の前までに摘んでしまわないといけないと、母が今日急いで摘んでいたのを手伝っていたのでした。この満月を逃すと、次の満月の前には芽はみんな葉になり硬くなってしまうのです。『魔法使い』と言ったら、満月の前後には色々やることがあるのです。
母が『ルーファンの書』を調べ始めるとなかなか終わらないのを知っていたキトは、その場に腰掛けると、休憩用に置いてあるカップに去年作ったカヤのシロップを注ぎました。そこに井戸から汲み置いてあった水を入れて自分の分と母の分を作り母の腰掛けているベンチに置きました。カヤのシロップジュースは疲れを取り、頭をすっきりさせてくれます。まだほんのり肌寒い春の午後、キトは斜面になった庭から美しい森を見下ろす様に立っている小さな家を背に父のことを想いながらジュースをすすりました。辺りは春の黄緑色の光を受けてさらに発光する様に輝いていました。優しい光の粒が舞うこんな春の日がキトはたまらなく好きでした。隣でシロップのジュースに気がつかないほど『ルーファンの書』に集中している母の横顔は、春の光で一層輝いて見えました。発光するような金色の美しいカールのついた髪を後ろで束ねた母は、魔女にしておくには勿体無いほど可愛らしい女性でした。華奢な手は陶器の様白く、美しい爪は指の先で輝き、こうして庭に出て作業をする必要がないのなら家の中で何もしないで大事にしておいてほしいのにと思うほどでした。髪と同じ色の金色のまつ毛は、濃い紫色のスミレの様な瞳を柔らかく縁取り、笑うと星屑が舞う様に光る母の笑顔がキトの心からの自慢でした。キトの髪は父に似てオレンジ色になってしまったので、母の金色の髪はキトの憧れなのでした。
キトと母が、この小さな日当たりの良い丘の上の小さな家に住んでそろそろ1年が経とうとしていました。
キトの母は魔法使いでした。王立の魔法学校も出ているし、そのあと尊敬する魔法使いの元で1年間修行もしてきました。母は本当に今まで真面目に魔法の勉強に取り組んできたのです。ところが、他の同じくらい修行をしてきた魔法使いに比べると、母は自信を持ってできる魔法が圧倒的に少ないのでした。母はそれが自分でもコンプレックスで、毎日の『ルーファンの書』での勉強を未だに欠かしたことはなく、良いと言われることは全てやってきました。それでも、まだ『ルーファンの書』なしでは魔法を使うことは不安だし、箒に乗って飛ぶことに至っては、小さな木を飛び超えることくらいがやっとなのでした。また、一人前の魔法使いは、普通何かしら動物が一緒にいます。自分で買いにいくこともできましたが、魔法使いのプライドとしては、動物の方から来てくれることが理想でした。立派な魔法使いと言われる人たちには必ず賢い動物が向こうから一緒にいたいとやって来てくれるのです。母はそれをずっと待っているのですが、一向にそのような動物は現れませんでした。一番好きな、植物を使った魔法でさえどれ一つ自信のあるものはなく、それでこの丘の上の広い庭のある家で、まずは種から育てて魔法を理解しようと引っ越ししてきたのです。
キトの父カイラーはとても美しい妖精でした。父は母が魔法使いでもそうでなくても関係なく可愛らしい母その人を愛していました。母が魔法に関して落ち込んでも、父はただ笑って「大丈夫、マトは本当にすごい魔法使いなんだよ、だからマトらしくいたらいいんだ。マトが自分を大好きになるのが魔法への近道なんだよ。」というのでした。キトは、そんな時、パパはママが魔法ができようができまいが、まったく関係なく母を好きなのだと感じました。時々父は母の魔法を手伝ってあげましたが、そもそも妖精の魔法と魔法使いの魔法は違う、と母は言います。母の魔法は思った様な結果にならないことがほとんどで、父はそんな母が可愛くて仕方ないというのでした。母は、自分の気持ちを本当の意味で理解していない様に見える父からは、元気付けられることがありませんでした。母はいつも自分ができないことに視点を向け、父は母の存在そのものに視点を向けていたのです。
母を大切に大切にしてきた父に対して、母はどの様に接したらいいのかわからなくなっていきました。一向にできる様にならない魔法に対しての不安と苛立ちを、父は笑って大丈夫、絶対うまくいくから、もっとリラックスして自分を大切に、と言うだけでした。優しい父に対して母が笑顔を向けられなくなったある日、父は急に旅に出ることにしたと言って、愛する家族を残して出て行ってしまいました。今ここに父がいない方が良いというのです。
「マト」
父は愛する妻にいつもの様に心を込めて呼びかけました。
「僕は必ず帰ってくるよ。可愛い君のそばで見守っていたいというのが僕の本心なんだけれど、多分君の魔法にはそれが良くないんだ。その確信が強いから僕は行く。」
そして、父は娘に愛情いっぱいの瞳を向けて言いました。
「キトはママを支えてあげてね。キトにしかできないことがあるから。大丈夫、君たちなら助けてくれる人がたくさんいるよ」そうやって妖精の祝福を授けて行ってしまったのです。
母も娘も最初は唖然としました。ですが父はあっという間に行ってしまいました。妖精とはそういうものなのです。
父は本当に出て行ったきり帰ってきませんでした。母は気持ちを切り替えるためにこの丘の上の家に越してきたのです。一体何がどうなったら父が帰ってくるのか、はっきりしたことはわかりませんでした。それでも、何か母の魔法に関することなのだと二人とも感じていました。母は、自分が立派な魔法使いになるまで、夫は帰ってこないのだと思い、キトもそう思いました。それで、キトは母が立派な魔法使いになれる様、できるだけ手伝おうと心に誓いました。パパは帰って来たいのだ、でもママの魔法の修行にはパパがいてはダメだと。母は、自分の不甲斐なさから愛する夫を遠ざけてしまったことに胸が張り裂けそうでした。しかし、夫がなぜ今ここにいないかは十分理解しているつもりでした。あとは やるしかないのです。
魔法使いと妖精が結婚することは珍しいことではありませんでした。その間に子供が生まれると、その子は魔法使いか妖精かどちらかに似て育ち、そのうちはっきりとどちらかになることが多いのですが、12歳になったキトにはまだ自分がどちらに似ているのかわかりませんでした。キトはママの様に魔法にそれほど情熱があるわけでもなく、かといって他人より自分を大事に、自由に今を生きているような妖精の価値観も理解できないところがありました。しかし母を見ていて、努力して努力してそしてたくさん守るべき規則で囲まれた魔法使いの人生は自分には無理だと思っていました。それならばきっと自分は妖精なのかな。キトはそう感じていました。
キトは眩しい春の太陽に照らされて少しずつ乾燥していくカヤの輝く黄色の葉を手のひらで撫でながら、一生懸命『ルーファンの書』を読みふける母と、母が大切にしているこの丘の斜面の庭を見て、今までの一年を想いました。
母の庭は、『ルーファンの書』の理想その通りに作られていました。太陽の道筋にぴったり合わせた小石の通路や、苦労して集めて来たふかふかの土、悪い虫を寄せ付けない様に、大切な植物の周りにたくさんの強い香りのするハーブを植えたり、魔法の道具やお守りを置いたりしました。また、『ルーファンの書』では理想的とされる、庭の縁を流れる小さな小川が母の自慢でした。この小川は、本来は庭の中央を通っていた小さな雨水の流れだったのを、母とキトと二人で何日もかけて石を積み、流れを変えて庭の縁へ行く様にしたのでした。もともとあった流れというのは、雨が降ると庭の中央の土をいくらか削ってくぼみを作っていたのですが、そこには大きな石をたくさん埋めて土をかけ、生活に役立つ強いハーブをたくさん植えました。最初、この様な場所に何を植えたらいいかわからず、『ルーファンの書』で研究もしたのですが、結局よくわからないので、強いハーブのタネが余っていたのをそこに無造作に蒔いたのです。今のところそのくぼみのハーブの花が庭中で一番よく育っていて、庭の中央を美しい色と香りで染めていました。
満月の光を効率よく庭にエネルギーとして広げると言われていた、小さな「渦巻きの丘」も母の自慢でした。これも、キトと母の二人で『ルーファンの書』の理想通り、庭の中央から南東へ少し下ったあたりに念入りに配置しました。何日もかけてあちこちから土を運び、並べる石も、種類や色や大きさをきちんと揃え、月の光を美しく反射させて光を庭に広げられる様になっていました。石の配置や種類はとても大事で、このためにわざわざ市場の石屋から質の良い高価な石を取り寄せ、長い時間待って月の光を見ながら埋め込んだものもありました。この渦巻きの丘は『ルーファンの書』を何度も何度も読んで幾度となくやり直し、やっと本の通りにできた時には二人でその渦巻きの丘で満月の光の下、嬉し涙をこぼしたものでした。
そんな大切で大好きな庭でしたが、実際はうまくいかないことの方が多いのでした。いちばん期待していたガレリアの花園は、ほとんどダメになりました。ガレリアはほとんどすべての魔法の基本で使われる花なのですが、花が蕾をつけた途端虫にやられてしまいました。葉は白っぽいカビに覆われ、どんな薬も大して役に立ちません。かろうじて助かった蕾が開いて花を咲かせても、次の日には花の中に虫が寝ているのを見つけるのです。結局秋になる前にほとんどの花と葉は落ちてしまったのでした。
また、日当たりさえ良ければ丈夫に育つと言われているウルカイ草は背丈だけがどんどん伸びて、風の強い日に皆折れてしまい、支えをつけたものの、小さな花が少し咲いただけで終わってしまいました。ウルカイ草は、乾燥させた花を、魔法陣(*1)を描く時に使うのでたくさんあると重宝するのですが、今年はほとんど収穫できませんでした。
*1魔法陣:魔法をかけるときに、地面や紙に描く模様のこと
そして、あんなに苦労して作った「渦巻きの丘」は、期待したほど月の光を集めてくれないのです。『ルーファンの書』によると、渦巻きの丘に満月の光が注がれると、光る石の効果で満月の光は丘の中央に渦巻きに沿って集まり光の玉を作ります。その玉が十分な大きさになると弾けて庭中の植物に溶け込み、それだけで植物は自らの力を存分に出せるエネルギーを蓄えられるというのです。しかし、母の渦巻きの丘は、どれだけ石の配置を変えてみてもうまく光を集めることができませんでした。『ルーファンの書』に書いてあることは全部試したのにダメでした。
「どうしてかわからないのよ、私は『ルーファンの書』に書いてあることを一言一句間違えずにきっちりやってるというのに、何もかもちっともうまくいかないの。学校で習ったことも、魔法使いの先生の元で修行した時も、言われたことで『ルーファンの書』に書いていないことはみんなメモしてこうして擦り切れるほど読んでいるのに。もうこれ以上何を努力したらいいか見当がつかないわ。パパだってこれじゃあ帰ってきてくれないわ・・・」
母は一度だけこう言って満月の日に窓辺で涙を流しました。キトはそんな母に寄り添い、一緒にそっと泣くのが精一杯でした。一体、世の中の魔法使いはどうやって様々な魔法をいとも簡単にこなしているのかしら。母はここで一人でやっていて、果たしてうまく行くのかしら。キトは考えてもわからないのでした。
母の頼りは今や『ルーファンの書』だけでした。夜遅くまでロウソクの灯りで『ルーファンの書』を読みながら何かブツブツ唱えている母の不安気な声を聴きながら、キトは母の作った柔らかい良い匂いのするキルトをかぶって、一体どうしたら母が良い魔法使いになれるのか、いつも心にモヤモヤしたものを感じながら眠りにつくのでした。
「キト、いろいろ読んでみたけど、マータルの花粉を集める満月の日が雨だった場合はどうしたらいいのか書いてなかったわ・・・」
母は自信なさげにキトに言いました。
「どうしましょうね、この花の上に屋根をつけて満月の明日花粉を収穫するか、それとも今日収穫してしまった方がいいかしら・・・」
「花粉はなぜ満月の日じゃないと収穫してはいけないの?」
キトは何気なく疑問に思って聞きました。
「満月の光が花粉に一番強いエネルギーを与えるからと書いてあったわ。」
それなら、雨の日に収穫しても今収穫しても満月の光が当たらないのだから大した差はないのではないかとキトは感じました。でも、母はそれがわからないのでしょうか。どうして母はこういうことになると途端に自信がなくなって決められなくなるのかしら・・・
結局二人は、マータルの花粉を今日中に収穫してしまうことにしました。そして、また来年、きちんと満月の光を浴びた花粉を収穫できれば、今年のものと比べられるからという結論に達しました。
そうしようと決めたのは、たった12歳のキトでした。
キトは、こういう時のママを見るのが嫌でした。自信があまりにもなくてかわいそうな気持ちになるからです。ママはなぜこんなにできないのにいつまでも魔法使いになろうと頑張るのか、キトにはわかりませんでした。実際ママは、魔法以外のことになると別の人の様に生き生きとしていました。パンを焼いたり買い物に行ったり、他所にお茶に呼ばれてお菓子を焼くママは素敵でした。ママのパンは評判になる程絶品だし、お菓子もたくさんの人がレシピを聞きにきました。それにママは誰よりも綺麗で、所作が美しく、魔女にしておくには勿体無いほど可愛らしい人でした。パパはこんなに素敵なママをいつも見られないなんて、きっと今頃寂しがっているだろうと、キトは切ない気持ちになるのでした。
でも、ママは心の底から魔法使いに憧れていました。どんなにできなくても、どうしても諦められないのがキトにも伝わってくるのです。ママは身体中で魔法を愛していました。魔法と聞くだけでワクワクしてしまうのです。『ルーファンの書』に書いてあることは不思議でいっぱいで、眺めているだけで楽しいのだとママは言うのでした。
「ちょっとお邪魔するよ」
「まあ、モーラさん。こんにちは」
モーラさんは、麓の村のおばあさんで、ここへ引っ越してくる時から随分とお世話になっていました。
モーラさんはママのパンに惚れ込んでいて、いつも美味しいスープや卵などを持って来てくれるので代わりにママのパンをあげるのです。飼っている牛も、モーラさんが、ミルク入りの柔らかいパンを焼いてくれるなら、と気前よく譲ってくれたのでした。
「今日はうまい具合に春の菜の花のスープができたものでね、持って来たんだよ。」
言葉はぶっきらぼうでしたが、モーラさんは母娘が感謝しても仕切れないくらい良くしてくれるのです。
「菜の花のスープ、美味しそう!」
キトが嬉しさで飛び跳ねると、モーラさんはフンと鼻息を鳴らしました。
「子供には苦いかもしれないよ。」
「モーラさん、どうぞ中に入ってお茶でもいかがですか?」
「いや、わたしゃこの後まだ何件か回ってスープを配るもんでね、あんたのパンをもらえたらと思ったのさ。それに見たところ、あんた方も忙しそうじゃないか。」
「今終わったところですのよ、このマータルの花粉をちょうど瓶一杯にしたところです。さあさ、遠慮なさらずに中にお入りくださいな。」
母は、モーラさんがわざと忙しそうにして母娘の仕事の邪魔をしないようにしてくれている優しさにいつも気づいていました。ぶっきらぼうなモーラさんは、本当は母娘とお茶をするのがとても好きなのです。モーラさんは、また鼻でフンと息を鳴らしながら、でも嬉しそうに言いました。
「それじゃあちょっとばかりいただいていこうかね。」
モーラさんとお茶をする時間はいつも、ママは輝いているように見えました。お茶の用意をするのがママは本当に上手なのです。どんな魔法使いも負けないくらい、美味しいお茶をママは淹れることができました。そして、モーラさんはぶっきらぼうなのですが、根底に大きな愛を感じ、家の切り盛りや動物の世話など豊かな経験から役立つことをたくさん教えてくれました。モーラさんは母と娘しかいないこの小さな家にかけがえのない安心感を与え続けてくれるのです。本当にありがたい存在でした。でもモーラさんとは魔法の話はほとんどしたことがありませんでした。モーラさんは魔法使いではないし、ママの悩みを話したところで鼻でフンと笑われそうだねと、キトとママはよく笑って話すのでした。
2.魔法の会
ある朝、興奮で頬を赤く染めた母が、顔を洗ったばかりのキトに言いました。
「キト、聞いて。今朝の魔法新聞に出ていたの、私の魔法使いの修行時代の先生が新しい魔法の会を開くそうなのよ。これを見てちょうだい。」
キトは朝食の皿をテーブルに置きながら待ちきれない様にして新聞を皿の横に広げました。
「大魔法使い、イレーンの魔法の会、特別編。何年も魔法をやってきて、未だにうまくいかない、自信が持てない、覚えたと思っても成功しない、そんな経験はありませんか? そんなあなたにぴったりの会を開きます。紫陽花の月第2の日から7日間。場所はブラーフの森イレーンの館。会に入るには、大切な思い出の品との交換です。お手紙でお早めにお知らせください。」
「ママ、これに行ってこようと思うの。この魔法の会の内容は今のママにぴったりだと思わない?ママのおばあさまのあの手彫りのカトラリーを交換しようと思うの。」
母はキトが読み終えると同時に勢いよく話し始めました。
「ブラーフの森はここから歩いて5日はかかるわ、往復で10日、それに魔法の会の日にちを入れると少なくとも17日間は家を開けることになるのよ。」母は箒で飛んで行けるほど飛べないので、歩いて行くしかないのでした。
「ママは箒が使えないでしょう?でも持って行くつもりなの。もしかしたら飛び方も教えてもらえるかもしれないし。これが最後のチャンスだと思って、聞けることはみんな聞いてくるつもり。キト、一人でお留守番できるかしら。」
キトは久しぶりに元気な母の声を聞いて自分も元気になるのを感じました。箒は自信がないので見ない様に納屋にしまってあるというのに、それを出して持って行くというのです。一人で何日も留守番などしたことがないので不安ではありましたが、それよりも母がこんなに喜んでやる気を出していることが嬉しくて、キトは母を安心させる様に言いました。
「ママ、もちろん私なら大丈夫よ。パンの焼き方もスープの作り方も、洗濯も掃除もみんな教えてくれたでしょう?ママが出発するまでにもう少し自信がつく様に練習するから気になるところは教えてくれたらいいわ。」
「そうね、あなたは器用だからうまくできるわ。庭のことで私がやってほしいことはみんな紙に書いておくから、最低限のことをやってもらえばいいわね、時々様子を見に来てもらうようにモーラさんにも頼んでおくわ。キト、本当にありがとう。ママ頑張るわ。」
母は早速、手紙を書いてイレーンの魔法の会に申し込み、出発までにたくさんの本を集めました。キトの胸が痛んだのは、ママの持ち物で宝物にしていた手彫りの美しいカトラリーを魔法の会に出してしまうことでした。セラという珍しい木でできたそのカトラリーセットは、美しい植物の彫刻がなされ、油分の多いセラの実から採れるオイルで磨かれていて固くしなやかなため、とても貴重なものなのでした。セラの木は魔法使いが皆憧れる海の向こうの小さな島、クル島でのみ特別大きく育ちます。この島で作られたセラの加工品は、魔法使いにとっては自慢の品で、おばあさまが特別に譲ってくれた母の宝物だったのです。魔法使いは、自分にとって大事なことをするときや、何か人生において大切なものを受け取る時、それに見合う価値のものを自分の持っているものから出すことがあります。自分の愛やエネルギーを込めたものを差し出すことはそれだけの価値のあるものを受け取ることができると信じられてきました。だからキトは母の気持ちはとてもよくわかりました。この魔法の会に人生をかけている意気込みが伝わってきました。キトはその美しいカトラリーを眺めるのが大好きだったのですが、その普段使っていない宝物よりも、母の成長できることの方がよっぽど嬉しいと自分に言い聞かせました。
「おばあ様のこのカトラリーは愛がいっぱいだものね、交換すればきっとうまくいくに違いないわ。」
母はいつになくウキウキし、良い流れに乗っていると何度も言いました。
魔法の会の前までに読んでおいた方が良いと言われた、イレーンが書いた本も全て取り寄せ、念入りに読んで記憶できることはみんな頭に入れました。「『ルーファンの書』は持ってこない様に」魔法の会の説明書の持ち物のところに、太字でこう書いてありました。
「『ルーファンの書』を使わないなんて不安だわ。ママはまだこれがないとうまく魔法が使えないのよ。」
「でも、持ってこない様にってわざわざ書いてあるということは、『ルーファンの書』には書いていないことを習いに行くのかもしれないわよ。それに、歩いていくのだから、どっちみちあれを持っていくなんて無理よ。」
「そうね、キトの言う通りね。こうして魔法の会に必要な本もみんな読んだしね。とても緊張するわ。もしうまくいかなかったらどうしようって思うのよ。」
「ママは大丈夫よ。ママほどたくさんの本をきちんと読んでる魔女はいないわ。あと少し、何かのきっかけできっと全部うまく行く様になるわよ。」
キトは今までずっとそう思ってきたことを言いました。その少しのきっかけが何かわからないのだけど、とにかく絶対あと少しなんだと、キトはずっとそう感じていました。きっとパパもそう思っていたに違いない、パパに会える日が近づいているかもしれないと思うと、二人とも興奮で毎日落ち着かないのでした。
春にしては薄寒い風が吹く霧の朝、母はブラーフの森へ、魔法の会のために家を出ました。
キトは初めてこんなに長い間家を一人で切り盛りすることに実はとても緊張して、夜は心配で少しも眠れず、朝は手が震えるほどだったのですが、母にそうと気付かれずに見送ることができました。母はそれ以上に緊張していたからです。キトは食欲のないという母に、昨夜たっぷり作っておいた春の山菜のスープを温めて飲ませ、たくさん焼いたどんぐりのパンを清潔な布巾に包んで持たせました。母は、キトが一緒にスープを食べていないということにも気付かないくらい緊張していました。ずっと納屋にしまってあった箒を持つと、トボトボと歩いて朝の霧の中へ消えて行きました。講座を受けられることは喜びではありましたが、もしこれで魔法ができるようにならなかったらと思うだけで二人とも怖くてたまらなかったのです。
キトは、母が行ってしまうのを涙を飲み込みながら見つめていました。母は最後に一度振り返り、小さく手を振ると森の角を曲がって行きました。胸のあたりがシクシクと涙が出ているような気分になって、キトはしばらく呆然と家の入り口で立ち尽くしていましたが、霧をかき分ける様に朝日がキトの頬に当たると、今度は猛烈にお腹が空いて、残しておいたスープを全部平らげてしまいました。それから、家中の掃除を始めました。母には頼まれていなかったことも、何もかもやってしまおうと決心しました。キトは、魔法が使える様になって帰ってきた晴れ晴れとした顔の母が、家中全てが美しく磨かれているのを見てキトを嬉しさで苦しくなるくらいに抱きしめてくれる日を想像していました。そして、そこにニコニコしている父が加わっているのを胸の奥で念じる様に求めるのでした。キトは紙に母のいない日にちをカレンダーのようにして書きました。母がブラーフの森に着くまで5日間、ブラーフの森で魔法の会を受ける7日間、そして帰ってくる5日間、全部で17の四角を書いて、そこに印をつけていくことにしました。
キトが最初に手をつけたのは台所でした。これは思った以上にうまく行きました。全ての棚の中の瓶を出してテーブルの上に並べ、ラベルが擦り切れているものは新しく張り替えて瓶の表面の埃を丁寧に拭き、取り出しやすい様にまた棚に並べ戻しました。古くなっている箱に入った乾物や粉類は捨て、使えるものはしっかり拭いた清潔な箱や袋に詰め替えました。これは結構時間がかかったので、これをするだけで夕方になってしまい、キトは真っ暗になる前に急いで牛の世話をしてくると、台所で朝母に持たせたどんぐりのパンの残りをストーブの残り火で温めミルクにつけて食べました。食べながら、朝のスープの後、何も食べずに来たことに気づいたのでした。母はこのパンを食べただろうか、どこか安全な寝泊まりできるところを見つけられただろうか・・・部屋が暗くなってくると、キトはいつも母がする様にロウソクの瓶を3つテーブルに置き、火をつけて母を想いました。母がいない家は、一番大事なものがない虚ろな何かが広がっていました。ストーブに薪をくべましたがうまく火がつかないので、本当は今日のうちに終わらせなくてはならない細々とした家事をやり損ねたことを悔やみながら、疲れた体をベッドへ運び、明日またやりきれないくらいたくさんの仕事があることに不思議と安堵を覚えながら眠りについたのでした。寝る前に、カレンダーに印をつけるのは忘れませんでした。
最初の4日間は無我夢中でした。天気が晴れなのか曇りなのかも気にならないほどでしたし、お腹が空いたか空かないかもよくわからないほどでした。しかし少し風が吹いて家を揺らして音を立てるたびにキトはビクビクしました。暖かな春の日差しも感じられないほど寂しくて朝は泣きながら顔を洗いました。納屋の牛の存在も大した慰めにはならないのでした。母が行ってしまった翌日にモーラさんが顔を出してくれましたが、モーラさんの美味しい玉ねぎのスープも全然味を感じられませんでした。カレンダーに印をつける夜になると、一日が終わるのはなんと遅いことかと思いました。
5日目になると、一体母は無事に魔法の会を開く魔法使いイレーンの元にたどり着いたのだろうかと母のことばかり気になりましたが、6日目からはカレンダーに印をつけているおかげか不思議と、きっと母は今頃無事に辿り着いて魔法の会を頑張っているだろうと感じられて、自分も勇気が湧き、少しずつ地面をちゃんと歩いているかのように周りが見えるようになってきました。キトは母に言われたことはきちんと守り、一人でいることに少し慣れてきたので規則正しく生活できるようになりました。言いつけられていなかった家事もできるだけやりたくてやりました。窓を拭いたり、床を磨いたり、本を出して綺麗に拭いてまたしまったり、家中の埃をとったりしました。牛の世話も、今まで以上に念入りにしたので、牛は大層ご機嫌で、美味しいミルクをたくさん分けてくれるように感じられました。ちょうど牛の世話をしている時にモーラさんが顔を出してくれて、一緒に無言で牛の世話をしてくれました。この日はモーラさんが特別だよと言って色とりどりのキャンディーが入っている紙袋をくれました。不思議なことに、このキャンディを食べると心がスッキリして元気になる気がしました。
庭に関する母のメモはとても細かくて、朝の何時にどのハーブを取り、何時間きっちり太陽の光で乾燥させ、何時間以上は月の光に当てる、汲みたての泉の水で何回洗う、収穫するときは庭の入り口を箒で掃いて清める、収穫する植物によっては収穫するときの方角をきちんと守る、などとても気を遣いました。しかし、12歳の少女でもやろうと思えばなんでもできるのです。こうして毎日仕事を繰り返しやっていると、少しずつ自然が変化したり昨日あったものが今日はなかったりと、小さなことに気付いたり感じたりしました。母に言われたことは自慢したいくらいきちんとやってありましたし、それ以上に母が喜びそうなこともたくさんやってあるしで、キトは本当に母が帰ってくるのが待ち遠しいのでした。こんな風に、家のことや庭のことなど一生懸命取り組むうちにあっという間に母の魔法の会が終わる日がやってきました。
3.ルーファンの書
13日目の朝は冷たい雨が降り、一日中重く灰色な日でした。あと5日でママは帰ってくるはず。昨日で魔法の会は終わり、今日こちらへ向かう旅に出たのではないでしょうか。キトは誇らしげに印がいっぱいついたカレンダーを眺めました。もしかしたらママは箒の使い方を習って、半日で飛んで帰ってくるかもしれません。キトは今日の分の薪を家の中に運ぶと、まず暖炉に火を起こしました。こうして薄寒い雨の日に暖かな火を起こすのは心に勇気を灯す様な感じがします。パチパチと薪が弾けて炎を出す様子を見ながら、母は今頃家に向かってブラーフの森を出た頃かしらと想像しました。それから、牛の世話を急いでしに行くと、台所へ行って簡単な麦のおかゆを作り暖炉の前で食べました。
この日は家中の絨毯を洗って干そうと思っていたのですが、雨で干せないので他にできることはないかと考えて目についたのが、母の置いていった『ルーファンの書』でした。『ルーファンの書』は全部で六巻あって、そのうちの五巻は色々な分野に分かれているのですが、最初の1巻は魔法使いになる心得や心構え、どんな風にしたら良い魔法使いになれるのか、そもそも良い魔法使いとは何か、妖精との違い、魔法使いの歴史、魔法の種類などがまとめてありました。キトは、母がいつも大事にしているその本を読んでみようと思ったことはありませんでしたが、こうして時間がある今、何か自分が読んで母の為になることがあるのではないかとふと思い、そっと持ち上げ、暖炉の前へ持ってくるとページをめくってみました。
『良い魔法使いとはなんでしょう。』
魔法大辞典ルーファンの書はこう始まっていました。
『それには、魔法使いの様に魔法を使う妖精との違いを考えていく必要があります。
妖精とは、魔法そのものです。存在しているだけで魔法です。妖精のすることは、意図しなくとも魔法が宿り、美しい心の妖精であればあるほどあたりは愛のエネルギーで包まれます。そのため、妖精がそばにいるだけで幸福になることができます。また、心の中で魔法を作り出し、自分や他の人の幸せのために使うことも簡単です。妖精にはそれが生きている証しのようなものです。では、妖精ではない魔法使いはどうでしょう。魔法使いは、妖精と違い、存在しているだけでは魔法は出せません。魔法使いは、自らを知り、自らに正直であり、そうであるからこそ全ての大自然の信頼を得て大自然から魔法を分けてもらう存在です。自分一人ではできないことを、感謝の気持ちを持って他の存在の力を借りて人々を幸せに導いていくのです。言うなれば、エネルギーを循環させる役割を持っています。大自然と人を繋ぐのです。』
少し難しい説明だけれど、キトはなんとなく理解できたことが嬉しくて顔を上げました。
「それは知らなかったわ。」キトはなぜ今まで自分がこの『ルーファンの書』を開かなかったのか、少し残念に感じるほどこの本に興味を持ち始めました。
「私はママが魔法使いでパパが妖精だから、この二つの違いは体では感じていたしそれで充分だと思っていたけど、こうやって言葉で言われるとまだまだ知らないことがあるのね。」
たった12歳の小さな少女は、まるで大人になった様に得意げにひとりごとを言うのでした。
窓の外を見ると、雨はますます強くなっていくので、今日は最低限の家事をするだけで、あとはこの『ルーファンの書』を読んで過ごそうと決めました。この雨の中母は無事かしら。少しくらい帰るのが遅くなっても構わないから、安全な場所にいてくれたらいいなと思いながらキトは不安をかき消すために暖炉にもう一つ薪をくべて火を眺めると、温かいミルクにたっぷり蜂蜜を入れて持ってきました。リビングのクッションを集め、座り心地を確かめると、甘く香るミルクを飲みながら再び『ルーファンの書』を読み進めました。
『妖精は、起きたいときに起きて、寝たいときに寝ます。朝早く起きるのが大好きな妖精は早起きしますし、夜が大好きな妖精は夜ずっと起きています。やらなくてはならない仕事というのはなく、それぞれが魂の中から湧き上がる喜びで動いています。特筆すべきことは、彼らの《トーラ》という能力です。妖精たちは、一人一人必ず、トーラと呼ばれる自分が得意とする能力があります。彼らが生まれてから15年くらいの間に、そのトーラは出現すると言われています。例えば誰よりも早く飛ぶことができるトーラを持った妖精は、自然とその特技を生かした仕事を始めます。それは、自らがどうしてもやりたいという気持ちがトーラにより呼び覚まされる感覚です。トーラには様々なものがあり、植物と話ができたり、動物の声が聞こえたり、どの植物がどんな料理に変わるのか見ただけでわかったり、簡単な材料から何種類ものお菓子を作ることができたり、種を見ただけでどうやってその植物を育てるかわかってしまう能力など、ここでは数え上げられないくらいたくさんあります。その様なトーラのおかげで、妖精は自分がいつ何をしたら良いか、どこへいった良いのか、感覚的にわかるので、とても効率が良く、逆にそういった魂からのメッセージに従わないと体を壊してしまいます。こうしたトーラは一般的に妖精の生まれながらの仕事魔法と呼ばれています。』
キトは、パパのことを思い出していました。キトはトーラについてはあまりパパと話したことはないけれど、少しは知っていました。パパはよく、トーラは一つじゃない、何個も持っている妖精がたくさんいる、素晴らしいものだけれど、あまりトーラだけに囚われるのも好きじゃないって言ってたっけ。
キトが知っているパパのトーラは、他の人が持つ〈気分〉を、色や形で見ることができることでした。それで、ママが不安でいっぱいになっているといつも何も言わずに花を持ってきたり、どこかへ連れ出してママの周りに漂う色や形を変えるのだと言っていました。〈気分〉によって変化するその人のエネルギーの様なものの色や形を変える方法はそのときその時で違いました。どうやったらいいか、それはパパのハートだけが知っているのです。パパは、それを仕事にしていました。パパのところに相談に来る妖精や魔法使いは、パパが言うには糸が絡まっている様な形や、混ざってとても暗い色をしているのだそうです。その解き方をパパは知っているのでしょう。パパがこうしてみたらとアドバイスをして、その通りやってみたらうまくいったと言う人々が毎日の様にお礼の品を持ってきてくれたのを、キトは誇らしげに思い出しました。
そう思うと、パパはいつもママをどんな風に見ていたんだろう。パパが言ったアドバイスでママはうまくいかなかったのかしら。そもそもママはパパのアドバイスを聞いていたのかしら。キトはパパがママに対してよく困った顔をしているのを思い出しました。パパの能力が妖精の絶対的トーラなのだとしたら、なぜママを助けられなかったのでしょう。ママは知っていたのでしょうか、パパがどれだけすごい魔法を持っていたのか。
キトは『ルーファンの書』を読み進めました。魔法使いについての文章では、母はほとんどずっと赤線を引いていました。
『一方、魔法使いは自分を律することを基本とします。律するとは、魔法使いにとっては、“こうしなくてはならない”と言うことではなく、自らの欲求や喜びで自然とそうなっていくものです。そして、大自然の流れに自分を乗せていきます。朝は日の出と共に目覚め、夜は日没によって仕事を終えます。季節に寄り添い、風を読み、太陽や月の動きに自分を合わせます。朝は外に出て香りでその日の大まかな予定を決めます。月の動きは特に重要で、満ち欠けによって生活のリズムを作ります。大自然のエネルギーを最大限利用して魔法を作り出し、そしてそれを大自然に返していくのです。そうして大自然とリズムを合わせることは、自分を本当の意味で理解することにつながります。自分と正直に会話していくことで、大自然と繋がり、そしてそこで循環が生まれ、感動と喜び、安心と幸せに包まれます。自分を律するとは、自分が決めた仕事をきちんとこなし、その仕事の中で自分を見つけていくことです。季節ごとの単調な仕事の中で微妙な変化に気付き、言葉にできない美しさ、情緒を感じ取り、そこから学びを得ていきます。』
そして、次の文章は、母が赤い枠で囲み、何度も読んだと思われる形跡がありました。
『ですから何千、何万もの植物や鉱物、動物に囲まれた生活の中で、いかに一番良いタイミングでそれらの声を捉え助けをもらえるか、それは日々の生活の中できちんと自分を律して自分のリズム、自分の気持ち、自分の声を聞いていくことが基本となるのです。そうして、自らが大自然の一部として心穏やかに流れてゆく・・・良い魔法使いとは、それらが全てできてバランスが取れてるところからやっと始まります。 自分の声を聞けて初めて、大自然の声を聞くことができます。それはすでにそこにあり、流れていて、そしてその流れに乗るようにして理解していきます。』
キトは、少し複雑なこのママが赤い枠で囲った文章を読み返しました。それが魔法使いの基本だなんて思ってもみなかったのです。ママはどんな気持ちでこれを読んで線を引いたのだろう。そして、自分でも驚いたことに、この赤で印いっぱいになっているこの文章を読んで、キトはとても共感したのでした。自分のしたい生活は魔法使いなのではないかと、今まで少しも思わなかったのが、この文を読むと、自分の考えにとても似ているのでドキドキするのです。
母が今回意を決して参加した講座で、この部分をはっきりと理解できて帰ってくるといいなとキトは思いました。少なくとも、今の時点では、母は完全に理解していないとキトは思いました。自分のリズム、自分の気持ち、自分の声・・・母のそれを思った時、キトは不安になりました。母はいつも無理をしていた印象でした。自分の本当の気持ちに蓋をして、がむしゃらに頑張っていたとキトは感じていました。だから・・・こんなに頑張っているのだから、どうかうまくいく様に、といつも願っていました。そんな苦しそうな母を見て、それでもこれが魔法使いの人生なのだとキトは理解していたのに、このルーファンの書にはそれとは反対のことが書いてあるのではないでしょうか。
文章が難しいために、何度も読み返しては自分なりに考えをまとめることを繰り返していたので、集中するあまり時間を気にせずにいたキトは、ミルクのカップに口をつけてとても冷たくなっているのでハッとして時計を見ました。とっくに午後の食事の時間を過ぎていたけれど、それほどお腹が空いているわけでもありませんでした。
キトは立ち上がり伸びをすると、少し小走りでキッチンへ向かい、昨日焼いて大成功した柔らかくて丸いパンを真ん中で横に切りました。そこへ豆とハーブを混ぜ潰して固めたパテと庭の野菜を乗せて、もう一つのパンを重ねて皿に乗せました。熱い紅茶にたっぷり砂糖を入れ、暖かいストーブの前で食べるために小さなテーブルを運び、そこに食事を乗せました。
キトはしばらく、考えたくて、食べながら思いを巡らせました。
ママがあと少し何かを知ることができたら、良い魔法使いに近づくのかしら。残念だけど、ママはこれだけ勉強してもまだ入り口にさえ立っていないのかもしれない。キトは、ルーファンの書をもっと読んで理解してみようと思いました。難しいけれど、ママとは違った視点で読めるかもしれない。もしかしたら、ママは今行っている魔法の会できちんとそのことを教えてもらえるかもしれません。これでママがうまく行かなかったらということは考えたくなかったけれど、とにかく、自分がルーファンの書を読むことはママのためでもあるし、何より自分でも魔法使いに興味が出てきたので無駄にはならないでしょう。
外では雨がしとしと降り続いていました。どんよりとした雲は結局一日中太陽を隠し、湿った冷たい家を一層冷やしていました。キトは一度だけ雨よけのコートを被って牛の世話と今夜の分の薪を取りに外に出ました。牛は春の雨で機嫌が悪くなっていました。屋根のある場所へ行く柵がしまっていて牛が濡れてしまったのでキトは牛を屋根のある納屋へ連れて行くとしっかりと拭いてあげなくてはなりませんでした。雨が続きそうだったので、乾いた藁をたくさん牛の部屋に敷いておきました。薪置き場は屋根がついているので、薪がダメになることはないのですが、空気が湿っているので水気を含んだ薪は燃えにくく、キトは明日の朝の分も余分に運び、乾いた暖かい家の中で薪を乾かすことにしました。薪を運び終わる頃には辺りはすっかり暗くなり、キトはもう今日の仕事は諦め、手短に片付けると夕食のためのスープを作りました。キトはルーファンの書の続きが読みたくて仕方がありませんでした。今まで本を読んでこれほどワクワクしたことがあるでしょうか。ママのあの恋い焦がれるような魔法使いへの憧れというよりは、魔法の神秘を知りたい単純な好奇心ではありましたが、今まで自分が持っていた魔法への印象は完全に吹き飛び、妖精も魔法使いも両者それぞれとても興味深い存在となってきたのでした。
キトはスープを食べてきちんと片付けてからもう一度ルーファンの書を少し読んで寝ることにしました。
母がたくさんの赤い線を引いていた章から次の章へ移ると、魔法使いの歴史や妖精の歴史、いろいろな国のことや伝説、生き物や植物の絵がしばらく続きました。ここも、母のメモや書き込み、線でいっぱいでした。キトはこの大半のページはしっかり読むことはせずに、まずは飛ばして絵を眺めていました。そして、最後に数ページ、文字だけで書かれたページがありました。風について、水について、土について、火について・・・など、どれもこれもキトには興味のある事柄なのに、母は興味がなかったのでしょうか、今までびっしり引かれていた線がありませんでした。しかし章の初めの文を読んでキトは謎が解けた気がしました。
「ここからのページに書いてある事柄は、この後に続く二巻から六巻までの魔法の基礎をきちんとできるようになった魔法使いであれば、書いてあることの何十倍も理解でき、読むことに意味があります。ですから、ご自身が基礎はもう十分に自信があると心に準備ができたその時、この続きの章を読むことをお勧めします。」
キトはしばらく考えました。母は真面目に基礎ができないためにこの後の章を読まずにいるのだわ。私はどうしよう。
「私はまだ妖精なのか魔法使いなのかわからないのだから、読んで理解できなくとも読んではいけないということはないわ。」そしてページをめくり読み始めたのでした。
それはとてもとても不思議な話でした。今までの書き方と違って、まるで詩のようでした。
「風、それは意思がある。
見えるか見えないかはこちら次第。
こちらから近づけば、風は応える。
風は友となり寄りそい、かき混ぜる。
あなたを乗せてどこまでも運ぶ。
風の意思は風の愛。風の愛なくしては生きられない。」
「水、それは意思がある。
見えるか見えないかはこちら次第。
優しさと厳しさを見分けるべし。
命の源になれば、命を絶つ凶器にもなる。
感情を蓄え流れ動く。
水の意思は水の愛。水の愛なくしては生きられない。」
「土、それは意思がある。
見えるか見えないかはこちら次第。
数え切れないほどの命を蓄え
全てに適正な場所を示す。
愛を運び、愛を育む。
土の意思は土の愛。土の愛なくしては生きられない。」
「火、それは意思がある。
見えるか見えないかはこちら次第。
希望と恐怖を見分けるべし。
静の中に大きな動を持つ。
命の生まれる場所はここにある。
火の意思は火の愛。火の愛なくしては生きられない。」
「光よ、集まるのはなぜ。
それはそこに意思があるから。
石よ、光るのはなぜ。
それはそこに意思があるから。
星々よ、またたくのはなぜ。
それはそこに意思があるから。
草木よ、育つのはなぜ。
それはそこに意思があるから。
この世を満たす万物はこの法則にて
歌い踊り、語り、聴くものに応える。
心の目をよく見開き その意思を感じる、
受け取リたいものが受け取る
それが
全ての答えになる。」
4.嵐
そこまで読んだ時、不意に大きな物音がして、キトはびっくりして本を閉じました。先ほどまで静かに降り続けていた雨は止んだようでしたが、風が強くなり家を揺らしたのでした。それに続いて外の大きな木が葉を揺らしてうなりをあげました。たくさんの木が葉を揺らす音はとても風とは思えない大きな音を集めてぶつけてきます。キトは怖くなってろうそくを一つだけ残して消すと、その一つを持って2階の寝室へ急いで移動しました。家に当たる風は、壁や天井を揺らし、音を立てました。牛は大丈夫でしょうか…キトは布団に潜るとぎゅっと目を瞑って嵐が遠ざかるのを待ち続けているうちに眠りに落ちていきました。
ガタンという大きな音で目を覚ましたキトは、布団から顔を出しましたがあたりはまだ暗く様子がわかりませんでした。聞いたことのない風の唸り声は眠る前よりも恐ろしく奇妙な音を立てました。一層激しい勢いで家を揺らし、その振動で物が落ちるほどでした。この音はなんだろう、キトは震える手で毛布を自分に巻きつけて窓辺へ近づいて見ました。見たことのない激しい雨でした。風が飛ばしてきた雨は、まるでたくさんの石ころをぶつけてくるような音がしました。ガタガタと家は揺れ、窓ガラスが割れるのではないかと心配になる程雨はますます激しさを増し、キトは怖くて窓から離れました。あとどのくらいしたら朝になるのでしょう。窓の外は真っ暗な闇で、とてもまた朝がやってきてくれるとは思えないほどです。こんな嵐の中、ママはどうしているのだろう。急に押し寄せた恐怖と心配の波で、キトは声をあげて泣き出しました。まだ12歳の少女には大きすぎる恐怖でした。時折大きな音を立てて家が揺れると、キトはますます大きな声で泣きました。毛布を頭からかぶり、身体中が震えて止める事ができませんでした。
いったい何時間くらいそうしていたのでしょうか。少し風がましになって、家がそれほど揺れなくなりました。雨の音も、さっきよりは和らいだ気がします。すすり泣きながら恐る恐る毛布から顔を出し、窓の方を見てみると、うっすら明るくなっているのが感じられました。キトは、勇気を振り絞ってろうそくに火をつけると、まだ薄暗い1階へ降りてみることにしました。
家の中は、直接風が吹いたわけでもないのに、棚の小物や本が床に落ちていました。木枠に囲まれた小さな窓ガラスはたくさんのヒビが入っていて、びっくりして駆け寄ったキトは、割れた窓ガラスから外を見てろうそくを落としそうになりました。昨日雨だと思っていたのは大きな雹だったのでした。庭中に高く積もった雹は全ての草花をめちゃくちゃにして、美しさなんか御構い無しに辺り一帯を埋め尽くしていました。その上から今でも止みそうにない雨が雹をまとめて固めようとしているかのように降り注いでいました。
「こんな暖かい春に・・・」
春の草花も、大きな木に出た美しい新芽も、みんなボロボロになってまるで恐ろしい氷の魔法で殺された後のようでした。キトは夢中でドアを開けて、もう少し庭を見ようと外へ出ました。
一面の雹の山で寒々しい光景とは反対に、生暖かい雨が風に乗って家に当たりザザザと音を立てていました。
引きちぎられた草花や木の葉の青々とした香りが充満しています。植物を助けようにも雹の山で庭に入れません。全ての葉っぱはボロボロでした。ママの大切なハーブも、一緒に作ったアーチや柵や、新しく植えた苗、たくさん蕾を付け出した草もみんななぎ倒され雹に埋まっていました。降り注ぐ雨で、湯気のように霧が立ち込め、異様な世界に迷い込んだかのようです。キトの動く音で牛が反応し、心配そうに鳴いていました。牛は無事なようですが見に行かなければ。
でも何よりもキトは、さっきからお腹がチクチクするほどママが心配でした。こんな大変な嵐の中、ママは外にいるのでしょうか、それともちゃんと屋根のある安全な場所で避難しているでしょうか。それに、ママがもし無事に帰ってきてこの庭を見たらなんと言うでしょうか。あんなに大切にしてきたものが全てめちゃくちゃになってしまいました。キトが楽しみにしていたママの帰りは想像しただけでも悲しいものになってしまったのでした。
キトは家に戻ると、ソファの上にうずくまって座りました。割れた窓ガラスから雨の混じった風が家に吹き込み、外の草木のちぎれた香りを運びました。牛が鳴いています。何も考えられず、ママの事が心配で心は闇に落ちていくばかりでした。自分の体がここに無いような心細い感覚の中を漂い、ママがもし怪我や病気をしていたら、森の真ん中で倒れていたら・・・そう思うと怖くて体に力が入らなくなってしまうのです。
その時、ふと思いついて、キトは書棚の大きな地図帳を取り出し開きました。この家からブラーフの森までママを迎えにいくことはできるかしら。キトはできることはなんでもやろうと思いました。ほんの少しの希望を探し当てたことで、キトは自分がまだ息をしていることを感じました。心臓がドキドキ音を立てています。
地図を見ると、ブラーフの森までは小さな村を4つと大きな川を3つ越えて行く街道がありました。街道は、キトの家から丘を下り農夫の薪小屋を曲がって細い川沿いにある最初の小さな村を横切る、きちんと整備された黄色い煉瓦の道でした。キトは村に買い物に行くときに、いつかこの道をずっと先まで歩いて行ってみたいと思っていたのを思い出しました。
「街道をまっすぐ歩くだけだもの、簡単だわ。」
希望が湧いてきたキトは自分に言い聞かせると、早速台所へ行って、いま食べられるものを探しました。この間焼いたパンが少しと、フルーツを乾燥させたもの、そして花やハーブを砂糖漬けにしたものを使った長持ちするビスケットを瓶から出すと、油紙に丁寧に包み、カバンに入れました。そして箪笥から雨よけの厚手のコートと帽子を出ししっかりと着込むと、ためらわずに雨の中を飛び出して行きました。ただママに会えることだけを考えながら喜んで家を出たものの、雨足が強まり少し行っただけでキトはびしょ濡れになってしまいました。それに、思った以上に雹が積もっていてなかなか歩けないのです。暖かな春とはいえ、キトは雨に濡れた重いコートに染み込んだ水がすでに肌に当たって寒くなってきたことで不安になってきました。それでも、とりあえず村まで行ってみようと頑張ったのですが、農夫の薪小屋のところを見て愕然として立ち止まったのでした。薪小屋の傍を流れる小川は濁流となって薪小屋の薪を半分以上舐めるように流してしまっていました。薪どころか、薪小屋も危ない状態でした。濁流は、村まで続く小道になだれ込み、どこが川でどこが道かもわからないほどになっており、全く歩けないどころかかなり危険な状況でした。キトは自分の帽子に当たる雨のザザザという音が聞こえなくなるほどがっかりし、そのまま元来た道をトボトボと引き返しました。あの川の様子ではきっとモーラさんもしばらくは来れないかもしれない・・・。再び心が不安で埋め尽くされそうになるのをキトは歯を食いしばって逃げ続けるように歩きました。
キトは家に着いて、ドアを開けたとき、鍵もかけずに出たのに気がつきました。牛の声が聞こえます。考えてみたら、牛を置いて何日も旅なんてできないのに。すすり泣きながら、濡れた重いコートを脱ぎ暖炉の脇の椅子にかけると、乾いた服に着替えてから薪を集めて火を起こしました。震える手でマッチに火を付け、涙でいっぱいの目で見る暖炉の小さな火は、なんの希望にもなりませんでした。それでも、元気を出そうとさっき鞄に詰めたパンやビスケットを取り出してみると、油紙で包んだはずなのにしっとりと湿って冷たく、口に入れても美味しくありませんでした。あまりに寒いので、少し温かいものを食べようと、食料庫に向かって、乾燥野菜やきのこ、乾燥麦の瓶を取り出し、鍋に入れて水を注ぎ、火にかけました。
時折、窓の割れたところから風と雨がザザザと音を立てて入り込むのを、ぼーっと見つめながら、キトはすすり泣きが止まらず、泣きながらスープを作り、泣きながらスープを食べました。
キトは一生懸命今の現状から希望を探していました。ママを探しに行くのはもう無理だ。それどころか、あの川の状態や、まだ雨が降り続いていることを考えると、ママが帰ってくるのはいつになるかわからない…
温かいものを食べたので、少し気持ちが落ち着きました。キトは少し食べたことでより一層お腹が空いてきたので、さっき湿って美味しくなかったパンが火の近くに転がっていたのを、もう一度食べようと手に取りました。パンは火にあぶられて熱く乾燥していました。一口かじると、なんとなく香ばしさがあって美味しくてキトは驚きました。
そして、じっと火を見つめました。
「火、それは意思がある…」キトは昨日読んだルーファンの書の最後の詩を急に思い出したのでした。
そして、書棚に行ってあの最後のページをめくりました。
「火、それは意思がある。
見えるか見えないかはこちら次第。
希望と恐怖を見分けるべし。
静の中に大きな動を持つ。
命の生まれる場所はここにある。
火の意思は火の愛。火の愛なくしては生きられない。」
キトは、今まで当たり前のようにして使ってきた火が、目に見えないところでパンを温かく美味しくしてくれたことがなんとなく優しさに思えたのです。これほどまで心細く、これほどまで恐怖と不安に包まれた今、火という温かい存在が、まるで生き物のように感じられました。パンだけではありません。さっき作ったスープだって火がなければ作れなかったし、冷たくなったキトの体を温めることもできなかったでしょう。キトは、暖炉で楽し気に揺れる炎を見つめながら、心から言いました。「ありがとう」
そう言った後、心に暖かな火が灯った感じがしたキトは、立ち上がると道具棚へ急ぎました。
「まずは割れた窓を塞いでしまおう。」
キトはまず割れたガラスを片付け、薄い板や釘を使って、壊れた箇所をなんとか塞いで行きました。窓ガラスの壊れたところを全部塞いでしまうまでとても時間がかかりましたが、これ以上雨が家の中に入るのは困るので、一生懸命やりました。塞ぎ終わった時には、窓から入る光は前より少なかったけれど、隙間がなくなった分家の中がふんわりと温かくなってきました。
キトは、暖炉に新しい薪をくべて火に勢いをつけると、もう一度火に向かって言いました。
「ありがとう!」
雨はまだ降っていました。キトはやっと心に湧いた希望のおかげで、牛を見に行くことができました。牛は納屋の隙間から入る雨と風でベタベタでしたが、ここの壁も塞ぎ、床を掃き、かろうじて残っていた乾いた草を敷いて乳を絞りました。それが終わると、台所へ行ってミルクを漉し、一旦着替えました。
薪が残り少なくなっていたので、キトは乾いてきたコートをもう一度着ると、外に出てできるだけたくさんの薪を家の中に運びました。薪を触りながら、キトはずっと火のことを考えていました。この冷たくて重い薪の中に、あの熱い火の元になるものが入っているのです。
風はおさまってきましたが、雨はますます激しくなってきました。雹は氷の塊となって、まだ溶けずに草花を押しつぶしています。キトは庭は見ないようにしてひたすら薪を運び、家の入り口の中の壁いっぱいに積み上げました。雨がいつ止むかもわからないし、こうして薪を家の中に入れておけば乾いて火がつきやすくなると思ったのです。
その日は、窓の穴を塞ぐことと、牛の世話、そして薪を運ぶことで1日が終わりました。小さな女の子にしては大変な力仕事をよくやったとキトは自分でも思いました。降り続ける雨の音を聴きながら新しいスープを作り、明日はパンを焼こうと決めました。ママは無事かしら、モーラさんは大丈夫かしら。暖炉の火に薪をくべながら、キトは形の定まらない美しい舞を踊る炎を見つめました。
この家で動いているのはこの炎とキトだけでした。炎はパチパチと音を立てて話しているようでした。
「心配しないで。大丈夫だよ。今日はよくやったね。」
炎がキトにそう言っている気がして、キトは微笑み、「ありがとうね」と炎に手を振ると寝室へ向かいました。
ママのことは心配だったけれど、ママだって弱い魔女ではないのです。いつだってキトを引っ張って行ってくれる強い人なのです。きっと大丈夫、そう言い聞かせるとキトはもう一度炎を階段から見ました。炎に話しかけるなんて、今まではしたことがなかったけれど、こんなに心が温かくなるものなのね。炎は生きているんだわ。パンが温かくなったように、私の気持ちまで温めてくれた…
5.火の精霊
翌朝、雨はまだ降っていました。
暖炉を見ると昨日の熾がまだ残っていたので、キトは急いで細い枝と薪を足しました。
「昨日の火が残っているなんて、嬉しいわ。」
この火はキトの友達のような気がしてきました。朝の牛の世話をして戻ってくると、キトは思いついて、ルーファンの書の四巻にある、火の魔法を見てみました。火の魔法は危険もあるので、ママはあまりキトがいるところで練習してきませんでした。キトがページをめくっていくと、魔法初級のところに「火と会話をする魔法」というのがありました。
「火は生きています。意思を持っています。ですから、精霊を呼び出すことで今目の前にある火にはっきりとその火の意思が感じられるようになりますし、その火と会話をし、協力してもらうことができます。大きな火の協力を得るには、ある程度熟練した魔法使いでも難しいことですが、ロウソクや暖炉の小さな火であれば楽しい会話ができるでしょう。呼び出す火の精霊は、大抵その呼び出した場所に宿っている精霊です。場所が変わると、精霊も変わリます。ですが、蝋燭などの移動が可能なものにつけた火は移動してもそのまま付いて来ます。」
「これだわ!」キトは嬉しくて飛び跳ねると、なんとかこの魔法を習得したいと本にへばりつくようにしながら読み始めました。
「火と会話するためには、火と仲良くなり、信用を得ることが大切です。また、当たり前ですが深い感謝の気持ちも忘れないでください。必要な道具は消し炭をカップ2杯と、ハルニレの細い枝2本、ナナカマドの細い枝2本、麻紐、好きな花一輪、太陽の光を一日閉じ込めたはちみつをスプーン2杯」
消し炭は時々良質のものを壺に入れてあるので大丈夫。ハルニレやナナカマド、麻紐は魔法で使うのでママがたくさん持っています。キトは、庭に出て何か花が残っていないか探してみました。花はみんな雹でめちゃめちゃでしたが、家の屋根が庭に出たところの下の壁際に、小さなデイジーの花が開きかけていました。
「まあ、なんて幸運なデイジーちゃん」キトは摘んでしまうのが申し訳ない気もしましたが、株の根元にはまだたくさんの蕾がついていたので、デイジーにお願いして開いている花を一つ、そっと摘みました。
「デイジーちゃん、ありがとうね。」キトはデイジーの株をそっと撫でてお礼を言いました。
あとは、太陽の光を閉じ込めたはちみつね。
止まない雨の中、小さなデイジーを一輪そっと守りながら家に入ると、大切に水につけました。それからキトは食料棚のはちみつの大瓶を取り出しました。小さな瓶に少しとって移し、じっと窓の外を眺めました。いつになったら止むかしら、この雨は。
とにかく、材料はあと はちみつを太陽に当てるだけなので、キトは本の続きを読んでみることにしました。
「火に話しかけます。時間をかけて自分のことについて話します。できれば、その火に名前をつけると良いでしょう。
じっくりと気がすむまで自分のことを話し終わったら、火が燃えている周りを消し炭で丸く囲みます。高さは指の第1関節くらいまでが適当でしょう。ハルニレとナナカマドの枝一つずつで二つの十字を作り、真ん中を麻紐で結びます。二つの十字は、枝が重ならないように中心を合わせて8つの点を作り、中心を火に合わせて消し炭の円の上に置きます。ここで、好きな花を火に捧げながら呪文を唱えます。 パウサム、ルクラル、ミューレクラル、イレイラファレイラ、友よ来たれ」
これで火が応えてくれたら成功です。もし火が消えても大丈夫です。火が消えたからといって、火の精が死んでしまったわけではありません。ただ拠り所がなくなり、あなたと会話する術がなくなるだけです。また同じ場所でつけてあげれば戻ってきます。しかし、消さない方が精霊にとっては負担が少ないので、なるべく同じ火を絶やさず燃やし続けてください。太陽の光を取り込んだはちみつは、火の精の大好物です。時々あげてください。火が長持ちします。」
「あら、はちみつは後から準備すればいいのね。」キトは飛び上がると早速準備し始めました。
暖炉の真ん中辺りは家を暖かくしたり料理をするために必要なので、中心を避けて暖炉の隅っこの方に赤々とした熾を選び分けて置きました。小さな小枝をいくつか熾に置くと、パッと炎が立ち上がりました。キトはその炎に向かって話しかけました。
「こんにちは、私の名前はキト。私があなたの名前をつけるわね、ええと…ファルはどうかしら。温かい感じがしないこと?ファル、いつも私やこの家を温めてくれてありがとう。それから、食べ物を作る時手伝ってくれてありがとう。あなたがいなかったら、私たちとても寒かったり冷たかったりして、本当に困ってしまうわ。心から感謝しているの。ねえ、ファル、実は私今とても困っているのよ。困っているし、とても不安なの。ママがね…」
キトは何時間もファルに話をしました。パパのことも、ママの魔法使いの勉強のことや、庭がうまくいかないこと、とにかく思いつくことは全部話しました。今までこんなに自分の思っていたことを誰かに話したことがあったでしょうか。嫌だと思っていたことも、寂しさも、不安も、ファルに聞いてもらうだけでキトはどんどん元気になっていきました。途中で炎がなくなりそうになると、小さな枝を置いて炎を作りました。お腹が空いたキトは、ファルが消えないように注意しながら隣でスープを作り、食べながらもずっとファルに話しかけました。
とうとう、これ以上話すことがなくなったと思ったキトは、いよいよ消し炭をファルの周りに円を描くように並べ、ハルニレとナナカマドの枝を取り出しました。ハルニレとナナカマドの枝は、母が昔火の神様が宿ると教えてくれたことがありました。このことだったのかしら・・・麻紐でしっかり十字を二つ作ると、二つの十字の中心を重ねて8つの点を作り、そっとファルの上に乗せました。水につけて大事にしておいたデイジーでしたが、これをファルにプレゼントする、とキトは思いながら火の中にそっと入れました。そして本を見ながら、ゆっくりと間違えないように呪文を唱えました。
呪文を唱え終わると、キトはドキドキしながら待ちました。何も変化がないようです。それでもキトは辛抱強く待ちました。ママは大抵、こうやって魔法をやってみてもうまくいかないことが多いので、キトももしかしたら何か間違っていたかもしれないと不安になりました。揺れる炎のファルを見つめながら、もう一度魔法をやり直そうかなと思った時でした。ファルが上下にリズムをつけて揺れ始めました。伸びたり縮んだり、炎らしくない動きが続いた後、ポッと音を立てて黒い煙が上がりました。すると、キトの頭の奥の方から何か声が聞こえてきたような気がしました。キトは炎をじっと見つめました。
「ファル?」
キトが呼びかけたその時、ファルははっきりとキトの頭の中に応えました。
「キト!僕を呼んでくれてありがとう!デイジーをありがとう。」
キトは嬉しくてキャーと叫びました。
「まあファル!嬉しいわ!あなたと話すことができるなんて!」
「君はとても魔法が上手だね。僕の心にきっちり繋がってくれたから、本当に楽に出てこられたよ」
ファルは、話し方からしてキトと同じくらいの男の子のような感じがしました。
「私が魔法が上手ですって?まだ魔法使いかどうかもわからないのに?」
「君は魔法使いだろう?こうして僕を呼び出せた。それに魔法の修行をしてないって君は言ってたけど、それなのに一回で魔法を成功させたんだよ、君は間違いなく魔法使いだよ。」
キトは驚いたけれど、嬉しい気持ちでした。思ったよりも簡単に魔法が成功したことも驚きでした。
こうして、キトはファルと会話しながら1日を過ごしました。ファルは言いました。
「君のママはちゃんと無事だよ。でも、ここにたどり着くまでに大きな川が3本もあるだろう?今はまだ雨がやまないし、当分帰れないと思うな。」
「なぜ無事だとわかるの?」
「だって、僕はこの家の火の精だもの。家の持ち主のことはわかるよ。ママはちゃんと火のそばで暖かくしている。」
「そうなのね。」
とにかく、キトはひとまず安心しました。
「私、安心したらお腹すいちゃった。今日はパンを作るつもりだったんだけど、ファルも一緒に作ってくれる?」
「もちろん、僕がいつもパンを焼いているんだよ!」
ファルは得意げに縦に炎を揺らすとパッと黒い煙を出しました。
だんだんわかってきたのですが、ファルは感情が大きく動くとよく炎を揺らして黒い煙をパッと吐きました。
キトは、食料庫へ飛んで行ってパンの材料を取ってきました。少し気になったのが、食料庫にはもうあまり食料がないということでした。本当だったら、ママはあと3日後には帰ってくるはずなのです。食料もたくさん買っておいたけれど、予定の17日分を過ぎたらもうほとんどありませんでした。
「ファル、これが最後のパンになるかもしれないのよ。ママが帰ってくるはずの日までの食料しかうちにはないの。」
「嵐がおさまるといいけどね。村まで君一人で買いに行けないの?」
「たくさんは持てないけど少しの買い物なら大丈夫だと思うわ。ああ、早く雨だけでも止まないかしら。」
窓の外はまだどんよりと暗く、重い雲が下の方まで降りてきていて、大きな雨粒をたくさん降らしていました。
「雨には雨の考えがあるのさ」
ファルは当たり前のようにして言いました。
二人は楽しくパンを焼きました。生地をこねる間も寝かせている間も、焼いている間も、キトはこれほどおしゃべりをしたことが今までにないほどでした。ファルは色々なことを知っていました。今までこの小さな家には2人の魔法使いが住んだことがある、その時自分は呼び出されたけど、まだ家が建って間もない頃などは赤ん坊のようなファルに、魔法使いがいろいろなことを教えてくれたのだそうです。
「ああ、ファル、あなたに会えて本当に、どれだけ嬉しいかわかってもらえるかしら。」
焼きたてのパンを頬張りながら、キトは幸せそうにつぶやきました。
「僕も、今までの魔法使いの中で君が一番好きだな。君はなんでも話してくれてすごく楽しいよ。」
「いつかお日様が出たら、たっぷり光を浴びたはちみつをプレゼントするわね。」
「うわー、楽しみだなあ。太陽の味、大好きなんだ!」
キトは、ファルが喜ぶかわからなかったけれど、パンをファルにもあげると言いました。
「キト、大丈夫、僕はパンがなくても元気だし、君の貴重な食べ物なんだから、大事に食べてね。」
キトは寝る前に、しっかりとファルが消えないように少し大きめの硬い木をくべました。
「キト、大丈夫だよ。僕はこの消し炭に囲まれているから、消えにくいんだ。明日またね。ゆっくりおやすみ。」
6.意地悪
翌朝、キトはとても爽やかに起きることができました。何か、心の中で安心感が生まれ、精霊と繋がった喜びで満たされていました。飛び起きてファルのところへ駆け寄ると、ファルは縦に揺れて黒い煙をパッと出しました。
「キト!おはよう!よく眠れたかい?」
「ファル、おはよう!今日はぐっすり眠れておかげさまで元気よ!」
外ではまだ激しい雨が続いているようです。その時、庭で水や土が流れるような大きな音が聞こえました。
心配になってキトは窓辺に駆け寄りましたが、よく見えません。
「ちょっと見てくる!」ファルにそう言うと、コートをかぶり、キトは庭の音のする方へ行ってみました。
キトが驚いたことに、丘の斜面に作られたこの庭の、キトとママが一生懸命作った川の石は全て流されてあちこちに散らばっていました。そして、キトとママがこの庭を作る前にこの庭の中央に流れていた小さな川が、大きな流れになってそこに生えていた植物を根こそぎ流してしまっていました。流された植物はいくらか斜面の下の方に作った柵に引っかかっている状態でしたが、流れは勢いがあり、キトとママが作り上げたものはなんだったかもうわからないくらい破壊されていました。
月の光を集める丘も、美しい光る石を埋め込んであったところには泥水がたまり、石はもうどこにあるかわからなくなっていました。丘自体がぬかるんだ沼のように潰れていて、あちこちに立てた柵やアーチはほとんど倒れて泥に埋まっていました。びっしょり濡れて家に戻ったキトは、ファルの前に来ると無言でコートを脱ぎ、タオルで髪を拭いて体を乾かすために薪をくべました。
「キト?大丈夫かい?」
ファルが心配そうに聞きました。
キトは泣き出しました。
「ママと作った庭が全部流されちゃった。ママが立派な魔法使いになるために作ったのに。これじゃあせっかくママが帰ってきても、きっとがっかりしちゃうわ。それに、パパにいつになったら会えるのかわからなくなっちゃった。」
ファルはしばらく黙っていました。
キトが泣き止んで、少し落ち着いてくると、ファルはキトに言いました。
「キト。僕を呼んでくれたキトならきっとわかる。水も、風も、土も、みんなキトやキトのママを大事に思っているよ。だからわかってほしい。僕たちには意思がある。君たちの思った通りにならないことがあるならば、それは僕たちに任せた方がいいということだ。」
「この庭をめちゃくちゃにするのが、あなたたちの意思ということなの?」
キトは顔を真っ赤にして言いました。
「そうじゃない、そうじゃない。魔法使いの子、キト。この星の、この自然界に生きるということ、それは自然を君たちの意図で変えることじゃない、君たちが自然と共に流れていき、自然の手助けをしていくことなんだ。そうすることによって一層僕たちがなぜそうしているかが理解できるようになる。」
そして、ファルはそれっきり黙ってしまいました。
それから一日中、雨は散々降り続けました。キトはファルに言われたことがよくわからなくて、話しかける気も無くなってしまいました。庭がめちゃくちゃになったことがあまりにもショックでしたし、ママはやっぱり帰ってこないのでした。牛が鳴いて呼ぶので仕方なく世話をしに行きました。乳を絞ったけれど、今日はミルクを飲む気力もありませんでした。一度、どうしようもなく悲しくなって、キトは雨の降る庭に飛び出して行って、庭のあちこちに散らばった大きな石を集めて、もう一度川を作ろうと試みました。ママと一生懸命作った小川。それを、雨も風もなぜ壊してしまうのでしょう。意地悪をされているとしか思えなくて、キトは泣きながら石を集めて根気良く並べました。庭の中央にできてしまった大きな水の流れを、またこちらの作った小川に流せるように。中央の流れを堰き止めて新しい川へ流し込むことは、小さな少女には無理がありました。それでも諦めないでなんとか流れを変えてみせたキトは、大仕事を終えて家に戻りました。ファルが消えそうになっているのを見て、キトはゾッとして急いで乾いた小枝や硬い大きな木を手際よく配置しました。
パチパチとファルが戻ってきて、キトはホッとして体を拭きました。
「キト、どうだった?」
「やれることはやったわ。とにかくあの小川だけでも元に戻すことができたの。明日は雨が降っていても、月の丘の光る石を庭中から探し出して集めてみるわ。あれはとても苦労して集めた石なの。やれることはみんなやるつもり。」
ファルは無言で揺れていました。
ファルはなぜ返事をしないのかしら。
疲れたキトは、髪が乾くとパンを少しかじって、甘くしたハーブのお茶を飲み寝室に倒れるように入って眠りました。ファルはさっき大きな木をくべたから、消えないでしょう。
翌朝も雨が降っていました。ファルは無言だったけれど、キトは細い枝と太い木をファルの上にくべ、炎が上がるのを確認すると、無言でまだ湿っているコートを着て何も食べずに外に出ました。牛の世話をして、台所へ戻る前に庭を一目見ようと向きを変えたキトは愕然としました。昨日、あんなに頑張って作った小川は、また石が流されて散らばり、もっと勢いを増した水の流れが、庭の中央にどうだと言わんばかりに音を立てて流れていました。
キトは、庭を見ていられなくて家に駆け込むと、勢いよく二階に駆け上がり、服も髪も濡れたままベッドに突っ伏して大声で泣きました。
この家も、この庭も、私のことが嫌いなんだ。私とママが一体どんな悪いことをしたというの。風も、水も、土も、火のファルだって、なぜ私に協力してくれないの。
泣きすぎて腫れた目に、濡れた身体、そして心が折れてしまったキトは、そのまま起き上がることができず、その夜熱を出しました。
このままではいけないと、キトは一生懸命身体を動かして、乾かしたり着替えたりしようとしましたが、身体はずっしりと重く、力が入らないまま眠ったり目を覚ましたりしながら夜を迎え、そして朝を迎えました。
熱は下がるどころか、朦朧として、キトは寒くてガタガタ震えながら泣きました。
私はこのまま死ぬのかしら。ママ、パパ…
深い眠りから覚めたキトは、暖かなさっぱりとした布団に包まれて目を覚ましました。一階からとても美味しそうな匂いがしています。誰かがゆっくりと歩く音も聞こえます。きっとママが帰って来たんだわ。キトは目から涙が滲み、心の底からホッとしましたが、あの庭を見てママはどんなにかがっかりしただろうと思い、また目が熱くなって涙が出て来ました。ゆっくりと階段を登って来る足音が聞こえて、キトの寝室のドアがギイと音を立てて空きました。入って来た人物・・・背の低い真っ白な髪の毛を後ろで三つ編みに束ねたおばあさん・・・モーラさんでした。
「あたしゃ火の精に呼ばれたんだよ。なに、小さな子が食べるものもなく濡れたまんまで熱を出してると聞いたんでね。なぜ私が火の精と話せるのか聞きたいだろうけど、まずあんたはこれを食べて、ゆっくり寝て、元気になっておくれよ。それまでは私のことは黙っておくよ。早く元気になってほしいからね。」
モーラさんは懐かしい訛りのある口調で楽しそうに笑うと、キトの背中に枕を当てがって座らせ、口の中から唾が湧いてしまうほど美味しそうな匂いのするスープを、スプーンにすくってキトの口元に持って来てくれました。キトは怖くなるほど手にも身体にも力が入らないのでした。スープを飲んだだけで疲れてしまったキトは重いまぶたが目を塞ぎ、あっという間に眠りに落ちていきました。このスープ、いつか飲んだことがあるような、とても嬉しい味がする…
何回か同じようにモーラさんが来て美味しいスープを飲ませてくれた後、たくさん寝たキトは自分の力で起き上がれるようになりました。腕や足が少し細くなったような気がしますが、身体の中心からエネルギーが湧き上がって来ました。
「ファルは元気かしら」
ベットでモーラさんのスープを自分で飲めるようになったキトは、食べ終わると口を開きました。もう眠気はありません。
「あの火の坊やかい、消えかかってたけど大丈夫さ。別に消えたってあんたがまた魔法をやり直しさえすれば出てくるしね。今はあたしがこき使ってるから不満たらたらだよ。牛も元気だよ。今じゃよく乾かしてるからご機嫌だしね。」
モーラさんはいつものように可笑しそうに鼻を鳴らしました。
「あの、助けてくださって本当にありがとうございました。モーラさんはなぜ火の精と話せるの?」
「私は妖精なんだよ。今まで言わなかったけどね。あんた、本当に命が危なかったよ。あの火の精は本当にあんたが好きらしいね。」
モーラさんは、バターや甘い香りのするスパイスを温めたミルクに入れ、さらにたっぷりの蜂蜜を入れてキトに渡しました。
「あの小僧にもはちみつをやったよ。今じゃたっぷり日が照ってるからね。」
キトは、そのこっくりとした甘いハチミツやスパイスの入ったミルクをゆっくり飲み干しました。なぜかその味はどこかで飲んだことのある味でした。そうか、モーラさんは妖精だったのだ。こうやって美味しすぎる食べ物を作ることがモーラさんのトーラなのかしら。そんなことを考えながら、キトはまだスッキリしない頭でママを思いました。
「あの、ママはまだ帰って来てないでしょうか」
「よくもまああんたみたいな小さな子が一人で留守番してたもんだよ。おっかさんはブラーフの森まで行ったんだろう?そういう時は、村の誰かにあんたの世話を頼んだらよかったのにさ。私に言ってくれたらうちにずっとあんたを泊めたのにね。」
「私、一人でも大丈夫です。」
キトは赤くなって言いました。大声を出したつもりが、声は力なく掠れてしまいました。
「まあまあ、そう興奮しなさんな、まだ本調子ってわけにはいかないんだからね。大丈夫だよ、あの嵐はとっくに行っちまって、今はみんなして流された橋を直そうとしてるからね。だけどあんたのおっかさんは魔法使いなんじゃないのかい?箒があるだろうに。」
「ママはまだ飛べないんです。」
いよいよ顔を真っ赤にして、キトはうつむいてしまいました。
「ふん、時々箒に乗れない魔法使いがいるさね。どれ、あんたのおっかさんは一体いつ帰って来るやら。」
ぶっきらぼうな言葉に、キトはがっかりした気持ちになりました。
「さて、私の作ったスープやミルクは、あんたの身体をとことん癒すんだよ。もう一眠りしなさい。次に起きた時には下に行ってあの火の小僧っこと話せるくらいにはなってるだろうよ。」
キトはおとなしく言うことをを聞いて布団に潜りました。
確かに、身体は本当に良くなって来ていました。
7.自然の流れ
翌朝目覚めると、キトはまた一階で美味しそうなスープが煮えているのを香りで感じました。
伸びをして、恐る恐るベッドから降りてみました。
少しふらつきましたが、しっかりと歩けます。モーラさんにお礼を言いたくて、寝間着からきちんとした服に着替えると、キトはゆっくり一階に降りて行きました。
「キト!すっかりいいのかい?」
「ファル!ええ、もう元気よ。モーラさんはどこ?」
「おばあさんならもう行っちゃったよ。仕事が終わってやれやれだって、文句ばっかりさ。僕はこき使われて、えらい目にあったんだ。」
ファルは激しく揺れると黒い煙を何個も出しました。
「まあ、行ってしまったの?まともにお礼も言えなかったわ。このスープも作ってくださったんでしょう?」
「またきっと来るから、その時もっと作ってあげるって言ってたよ。だけどもう来て欲しくないや。僕どんなにか働いたか、キトは知らないんだから。」
キトは、食料庫をのぞいて見ました。新鮮な野菜やフルーツやミルクの他に、麦も乾燥キノコもたっぷりと瓶に入れてありました。キトはどうしたらいいかわからないくらい感謝しました。モーラさんは口は悪いけどやっぱり本当に優しい人でした。
「私どのくらい寝てたのかしら」
「そうだね、3日間くらいは寝てたんじゃないかな。外はとっくに晴れてるよ。庭を見に行くかい?」
3日間も寝ていたのだ、そしてママはまだ帰ってこない。
「ええ、まずこのスープを食べてからね。」
テーブルには新しく焼いたパンまで乗っていました。
あんまり美味しくて、キトはスープをお鍋の半分と、大きなパンも半分、たっぷりの蜂蜜を付けて食べました。
お腹がいっぱいで幸せな気分で外に出たキトは柔らかな風を頬に受け、青々とした夏の始まりの香りを思い切り吸い込みました。痛めつけられた植物は、それでもまた芽を出して生きていくのだとキトは確信しました。春の次に夏が来るのは自然の流れなのだわ。嵐の後に太陽が出るのも。だとしたら、水が流れていく道も、風が吹いていく方向も、土が芽を出す植物を助けるのも、みんな流れなのかもしれない。
そして、庭をゆっくりと歩き始めました。
キトとママが作った川はなくなっていて、そこにたくさんの小さな芽が元気よく出ているのを見つけたキトは、嬉しくて叫びました。「あら、これは見たことがあるわ。去年ダメになったウルカイ草に違いないわ。だけど、去年はこんなに強い緑色じゃなかったわ。」
水の流れはやはり庭の中央を遠慮なく流れていましたが、キトはこの流れの位置がこの庭にとても合っていると感じ始めました。小さな流れは、暖かい初夏の太陽の光を浴びてキラキラと光を辺りに散らしています。庭中が光で満たされているようでした。月の丘だった場所はドロドロしているかと思ったら、そこは窪みになって澄んだ水が溜まっていました。川から流れ込んでいたのです。もともとこの丘を作る前、ここには背の高い水草が生えていたのをキトは思い出しました。ここは斜面の下の方なのだから、水が溜まるのが自然なんだ…ルーファンの書には庭の南東に月の丘を作るべきと書いてあったから、絶対にここだと決めつけていたけど。」
庭には爽やかな強い風が吹いていて、キトの赤い柔らかな髪をかき混ぜるようにして通り過ぎて行きます。
庭の斜面の下の方へ、水の流れが作った小道ができていました。小道に沿って歩くと、行き着いた場所にはもともと生えていた生垣のようになった低木が集まっていて、そこにママと月の丘を作る時に高いお金を出して買った光る石がたくさん落ちていました。
「ここにあったのね。」
キトはしゃがんで石を拾い始めました。すると、そこだけ、風が当たらないことに気がつきました。ビュービューと風の吹く音はするのに、その低木の集まる窪みでは風がなく、温かい日差しがキトを優しく温めました。ここに果物を植えたらどうかしら。キトはふと思いました。日当たりが良くて暖かく、丘の上の強い風が当たらない場所なら、果物が揺れて落ちてしまうこともないでしょう。
家の入り口近くに戻って来たキトは、大きなカゴにいっぱいの紙袋が入っているのを見つけました。
紙袋を開けると、中には色々な種類の種が入っていて、一つ一つ花や草の絵と名前が記入してありました。カゴの持ち手のところにメモが貼り付けてありました。
「植える場所は土とタネに聞くこと」
「まあ!」キトはため息をつきました。
「なんだかわかってきた気がするわ。」
8.マトの絶望
キトの母マトは、あの大嵐の時、ちょうど最初の川を渡ったあとでした。
マトはイレーンの講座で、箒で飛べるようになんてならなかったのでした。それどころか、全く魔法ができるようにもなっていないし、かえってもう魔法なんて本当になんなのかさっぱりわからなくなって帰ってきたのでした。大声を上げて泣きたいのをぐっとこらえながら、マトはトボトボと歩きました。トボトボ歩いているうちに雨が降り始め、大きな木の下を雨宿りしながら渡り歩いて町まで向かっていました。マトは雨に濡れない魔法をかけるのもやめました。どうせやったって失敗して落ち込むだけだわ。今は魔法のことなんかこれっぽっちも考えたくなかったのです。町の入口が見えた時、少し雨足が強くなったので、大きめの木下で立ち止まってこぼれ落ちそうな涙を我慢しながらふと木の根元に小鳥が落ちているのに気がつきました。コマドリのようです。そっと顔を近づけると、まだ息をしているような気がしました。野生の動物に触るのは匂いが移ってしまうかもしれないと気が引けましたが、助けられるかもしれないとそっと手のひらに乗せてみるとまだほんのり温かさを感じます。しかし、濡れていてかなり弱っていました。
「なんだか私みたいね・・・」マトは肩を落として苦笑いしました。
「私は魔法が使えないからあなたを助けられるかどうかわからないわよ。でもここで私が連れて行かなかったらあなたは確実に死んでしまうわね。」
マトはかばんから柔らかいハンカチを出すと小鳥を包み、上着の胸の部分へ入れました。
町へ入ったマトは、小さな食堂と宿が一緒になった賑やかな店で、今夜一部屋空いていないか聞いてみるためにガヤガヤと人々が楽しそうに賑わう店内をそっと覗きました。
店内はちょうど夕食時だったため、美しいキャンドルに照らされた人々の幸せそうな顔と美味しそうな料理の食欲をそそる香りが漂い、ざわざわと賑やかで楽しげな雰囲気で満たされています。マトは全く食欲がありませんでした。使えもしない箒を入り口近くの傘立ての近くに置くと、ドアを開け、カウンターにまっすぐ向かいました。この暖かで笑いの絶えない食堂にはマトは場違いなほど沈み込んでいました。
「すみません」
忙しそうにしているカウンターの向こうの若い女性に向かってマトは声を絞り出して話しかけました。
「今夜の宿は空いてないかしら。」
「はい、ええと・・・今ちょっと手が離せなくて。待ってもらえますか?」
「ええ、大丈夫よ。」
若い女性はテキパキと丸いお盆にたくさんの形の瓶やコップをのせ、色とりどりの飲み物を入れて器用に席と席の間の狭い通路を飛ぶように歩いて運びました。お客と女性は親しげに話し、皆幸せそうでした。マトは、この世でこんなに不幸な私がここにいていいのかと居心地の悪さを感じながら、気分が悪くなって側の椅子に腰掛けて両手で顔を覆いました。胸元をそっと覗くと、コマドリが小さく息をしていました。
しばらくして、肩にそっと手を乗せられた気配で、マトはゆっくり顔を上げました。
「大丈夫ですか?気分がすぐれないのでしたら、すぐお部屋にご案内しますわ。一つだけ空いていました。」
「ええ、お願いできるかしら。」
「お食事はいかがなさいますか?」
「食欲がないので、結構です。ありがとう。」
「ではお部屋にご案内しますね。」
若い女性はカウンターのお盆にカップを一つ置くと、隣のポットにお茶の葉っぱをいくつかの瓶から選んで入れ、なみなみと湯気の立つお湯を注いでそれもお盆に載せました。
「では参りましょう。」
二人は食堂脇の階段から二階へ上がりました。上から食堂が見渡せます。席は満員で、笑い声や嬉しそうな小声や、食器のカチャカチャなる音が響いていました。
「奥様、こちらの部屋です。」
その女性は片手でお盆を持ち、片手で鍵を開けると、マトを中へ通しました。
「こちらに熱いお茶を置いておきますね。ゆっくりお休みください。」
「どうもありがとう。」マトは顔も見ずに言いました。
「奥様」
女性は部屋を出る前に振り返って言いました。マトは言われて彼女の顔を見ました。
「わたしはエテラっていいます。何かあったらいつでも呼んでくださいね。」
ドアが閉まってエテラが行ってしまうと、マトは小鳥をハンカチごとそっとテーブルの上に乗せ、自分は崩れるようにベッドに倒れました。
窓の外では、雨が本格的に降り始め、屋根にも激しい雨が当たってザアザア大きな音を立てていました。
本当に、マトにとって、こんなに辛い一週間はありませんでした。イレーンの魔法の会は全く何の役にも立たなかったのです。着いてすぐ、イレーンは生徒たちを集めて森の中で寝転び始めました。寝転んで何が見えるか、とか、草や木や空の雲と話をしようと言い始めました。魔法の話は一切ありませんでした。好きな木を決めて一日中会話をしろと言われたり、川の水に入って、流れに身を任せて感じたことを述べろと言われたりしました。訳がわからなくて怒って途中で帰る魔女もいたくらいでした。
イレーンは、なぜこれをするかをあまり説明してくれませんでした。ただ自然と会話をしよう、そしてそこでした会話をシェアしたり、その話をした木々や花に自分のしてほしいことを言ってみよう、そんな調子でした。
なぜこれをしているか、自分で感じてみてくださいと言うのです。
これは魔法使いとして、説明してわかることではない、自分で発見することだとイレーンは言うのでした。自分で発見できることなら、なぜこんなに苦労してここまで来たのでしょうか。教えてもらいに来たのに、自分で発見しなさいとはどういうことでしょうか。
そして、4日目の朝、突然魔法が使えるようになった魔法使いがいました。その魔法使いは狂喜していました。これまでなぜ自分が魔法が使えなかったかわかった、これでわかった、そう言ってイレーンと抱き合って喜んでいました。他の魔法使いたちはそれを見て焦りました。何がわかったと言うのだろう。しかし、そのわかったと言った魔法使いは、これは言葉では説明しにくい、とにかく自然と会話をすることだと言うだけでした。会話・・・何を話せと言うのでしょう。
そうして毎日同じようなことをして、最終日までに30人の生徒のうち11人の魔法使いが魔法を理解して喜びの涙を流すことができました。イレーンは言いました。
「今回魔法が使えるようにならなかった皆さんは、これで諦めないでください。この魔法の会でやったワークは、家に帰ってからも続けてください。いつか必ずご自分でわかる日が来るはずです。とにかく諦めずに、自然と会話をしていくことです。」
マトは身体中の力が抜けて崩れ落ちるほどがっかりしていました。
イレーンが言いたいことがなんなのかさっぱりわからなかったのです。本当にさっぱりわからないのです。
魔法を使えるようになる最後の手段が、自然と会話をすること・・・何を話すのでしょう?今日のお天気のことを?マトはそこに生えている草と話すことなど何もありませんでした。ききたいこともなければ、草なんかにお願いしたいこともありませんでした。マトは力なく笑いました。もう私には無理だわ。
マトは、宿屋のベッドの上でさめざめと泣きました。ようやく泣くことができた。
おばあさまの宝物のカトラリーを手放し、小さな娘を一人で留守番までさせて、何日も歩いてたくさんお金も使って、人生をかけて来たのに、わたしは魔法使いを辞めようという選択をすることになったのだわ。滑稽だこと。箒で空を飛んだり、植物の知識を人や自然に役立てたり、呪文や魔法陣で壊れたものを直したり、どんなにか憧れたことだろう。でもわたしなんかには無理だったのだわ。才能がなかったのだ。魔法の練習だって、人一倍やって来たつもりだけれど、回数ではどうにもならないのだわ。やはり才能なのだ。こんなことでもなければ諦められなかったのかもしれないわね、マトはもう苦笑いする元気もありませんでした。両親もおばあさまも立派な魔法使いだけれど、なぜ自分はこんなに落ちこぼれなのかしら。
そして、止まらない涙を一生懸命拭きながら、マトは思いました。
愛する夫、カイラーは、わたしのところに戻って来てくれるのかしら。魔法使いになりたくてもなれなくて、カイラーには嫌な思いをいっぱいさせてしまった。だけど、もうわたしが普通の人として平凡に暮らしたとしたら、カイラーは戻って来てくれるのかしら。たとえ、戻って来てくれたとしても、わたしは前みたいに笑えるのかしら。魔法使いを諦めるなんて、そんな日が自分に来るとは!
マトは泣きながらいつの間にか眠ってしまっていました。そして、大きな風が宿を揺らす音で目が覚めました。どのくらい寝ていたかわからないけれど、真っ暗な闇の中で大きな風の音が何度も建物を揺らすのは気分のいいものではありませんでした。窓から外を見てみようとカーテンを開けたけれど、窓は木の板で覆われていて、その板にバラバラと石のようなものがたくさん当たる音がしていました。
「雹だわ…キトのいる家もこんなに風が吹いているかしら」
マトは途端に心配になり、気持ちを落ち着けようと、さっきエテラと名乗った若い女性が淹れてくれたお茶をカップに注いで飲みました。お茶はもうとっくに冷たくなっていたので、ゴクゴクと一気に飲めてしまいましたが、そのお茶を飲んだだけで、不思議と気持ちが落ち着きました。コマドリの様子を見てみましたが先ほどと変わらず息はしているようでしたが目を閉じていました。マトは冷たくなったお茶を指に少しつけて鳥のくちばしを濡らしました。
階下ではまだ人がいて、何か話し声が聞こえます。マトは耳を澄ましてみましたが、はっきりと声は聞き取れません。風の音も気になるし、誰か何か知っているかもしれないと思い、思い切って部屋の外へ出て階下へ降りようと思いました。
9.魔法使いエテラ
「みなさん、落ち着いてください。このお茶を飲んで。大丈夫だから。心配しないで。」
先ほどのエテラが、不安げに何か話している他の客をなだめていました。
「この雨はしばらく続くと思います。風がいつもと全く向きが違うのよ。昨日から風の匂いも違ってた。念のため全部のガラス窓に硬い木の風除けをつけておいたから、窓ガラスが割れることがないといいわ。さっき外を見たら、雨じゃなくてかなり大きな雹も降っていたのよ。だから、みなさんできるだけ今は外に出ないでください。宿屋の部屋はいっぱいなのだけど、ここは食堂でもあるし食べ物もたくさんあります。こういう時は、風の流れに乗るのが一番いいのよ。逆らわないの。風は意図してこういった嵐を起こしてるのだから。」
「この若い魔女さんに従おう。」
贅沢な服装の紳士が言いました。
「若いがしっかりした魔法使いがここにいるのだから、我々は安心ですよ。」
そして紳士は、エテラの方を向くとウインクして微笑みました。
風はゴーゴーと唸りをあげ、建物を破壊しそうな激しさで雹がぶつかり大きな音を立てていました。
すすり泣く人もいました。
「必ず嵐はおさまりますから。それまではここにいてください。」
そう言いながら、エテラは一人一人に毛布を渡して回っていました。宿がいっぱいなので、休める場所がない人々は食堂で毛布にくるまって不安げにうつむいていました。
二階の廊下からこの光景を見ていたマトの視線はエテラに釘付けになりました。あの人は魔法使いなんだわ。
エテラは今はまた人々に温かいお茶を配っていました。
「気分が落ち着くお茶です。これを飲んでおけばしばらく寝なくても元気でいられるわよ。」
食堂の椅子なんかで寝られないと言っていた老婆に、エテラは励ますように言いました。
お茶を飲んだ人々は、しばらくするとみんな穏やかな表情で、じっと毛布にくるまり、眠り始める人もいました。
良いお茶をありがとう、と言ってお代わりを希望する人もたくさんいました。
しばらくして、エテラが一人になったので、マトは勇気を振り絞ってエテラに近づきました。
「あなた、こういうことをどこの魔法学校で習ったの?」
マトは前置きもなしにいきなり尋ねました。
少しびっくりした表情のエテラは、すぐに理解した様子で答えてくれました。
「奥様は、魔法使いなのですか?」
「マトよ。マトと呼んでくれたらいいわ。あなたどこの魔法学校へ行っていたの?」
「マトさん、私、魔法学校へは行っていません。ルーファンの書は持っていますが、誰かに習ったことはないんです。」
「学校へ行っていないですって?」
マトは驚いてしばらく口が開いたままでした。
エテラは少し恥ずかしそうに、でも微笑みながら言いました。
「昔から、植物や動物となんとかコミュニケーションを取ろうと色々やって来たんです。私は文字を読むのが苦手だから、本を読むと眠くなってしまって。それよりも、外へ出て実際に自分で見て触って聞いて、確かめるのが好きなんです。それを一つ一つルーファンの書で確認していったような感じです。ルーファンの書に書いてあることより、私が実際に考えてやったことの方が効果があったこともあります。」
マトは言葉が出ませんでした。
その時、家がとんでもなく強い風でグラグラ揺れて、大きな雹が窓の外の木の板に当たり、窓ガラスが勢いよく割れました。その場の空気が凍りつき、マトはびっくりしましたが、エテラは驚いている客をなだめ、冷静に割れた窓のそばに行くと、ポケットから何かの葉っぱとオイルを出し、魔法陣を素早く作るとつぶやくような呪文であっという間にガラス窓を元どおりに直してしまいました。
「ああ、あんた魔法使いだったね。」そばにいたおばあさんがにっこりしました。
「ここにこんな優秀な魔法使いさんがいるんだ、私ら大丈夫だよ。」
「私は万能じゃないわよ。このくらいの簡単な修復ならできるけど、家が潰れちゃったらこうはいかないわ。」
エテラが笑いながらそう言い、さっきまで不安でいっぱいになっていた人々の心を和ませました。
マトは頭の中も嵐のようでした。
「だって…だって…お菓子を作る時だって、きっちりレシピ通りにするじゃないの。魔法だってそうでしょう?ルーファンの書の通りにやるより自分で考えてやった方が効果があるですって?学校へ行ってないのに優秀な魔法使いですって?」
夜が明けて、まだ雨は降り続いていましたが、外の風はいくらか落ち着いて来たようでした。エテラは店の主人ともう朝食の用意をしていて、台所は何かを作る音や匂いで溢れ、人々は起き出しエテラが淹れてくれたお茶を雑談しながら飲んでいました。
「昨夜は随分とひどい嵐だったね。雹が積もって街道がうまく歩けないよ。」
宿屋の入り口からずぶ濡れの若者が入ってきました。
「さっきなんとか橋まで行ったんだけど、橋が流されちまってたんだ。とても渡れるようなもんじゃなかった。雨もまだひどいし。おいらは病気の婆さんに薬を頼まれてるんだ、早くあっち側へ渡れるといいんだけどなあ。」
「橋が流されるなんて、この100年聞いたことないね、とんでもない嵐だったんだねえ。」
食堂でお茶をお代わりしていたお客のおばさんがびっくりして言いました。
「私も橋の向こうへ行きたい一人だよ。困ったねえ、明日は友達に会う約束だったのに。」
そこへエテラが熱々のパンケーキを運んできました。
「ここにいて命が助かったのだから文句は言いっこなしよ。何か理由があって風や水が暴れてたんだわ。私たちにできることはこの安全な建物の下で楽しく朝食をとることよ。」
「とんでもないわ!」
マトは大声を出しました。
「橋が流されたですって!?12歳の小さな娘を家に置いてきたのよ。私が帰らなかったらあの子は飢え死にしてしまうわ!」
「誰かに任せてこなかったのかね?」
お茶のお代わりをもらいに行っていた老紳士がマトをなだめるように言いました。
「いいえ、あの子は一人なんです。」
「それでもマトさん、これにはきっと自然界の理由があるんですよ。落ち着いてできることを考えなくては。」
エテラがいい終わる前に、マトはエテラを睨みつけました。
「落ち着いてですって?子供がこの嵐の中一人でいるのに、落ち着いてパンケーキを楽しく食べていろですって!?」
マトは半狂乱になって建物を飛び出して行きました。
「マトさん、待ってください!」
エテラが叫んだのも聞かずに、マトは大雨の中街道を家に向かって走りだしました。
「キト!キトー!」
マトは夢中で走り、轟音の響く濁流になった川のところで立ち止まりました。橋は流されて数本柵が残るのみでした。一歩でも川に入ればあっという間に飲み込まれて命を落とすのは誰が見てもわかりました。茶色の泥川は、ただの川ではありませんでした。ありったけの力を込めてあちこちにぶつかりながら流れる水は、間違いなく止めることのできない意思を持って流れているのだと信じられるほど恐ろしい力がありました。
「キト!!!」
マトは壊れた橋のこちら側で泣き崩れました。雨が身体中を叩くように降り、これほど身も心も傷つけられたことはありませんでした。
不意に、誰かが肩に手を置きました。
「マトさん、ここであなたが倒れたら、娘さんを助けられませんよ。一度宿に戻りましょう。そして、なんとかできないか一緒に考えましょう。」
マトを追いかけてきたのはエテラでした。エテラは、マトを抱えるようにして立たせると、激しい雨の中を宿まで一緒に戻ったのでした。
10.魔法
エテラはマトを裏口から入れ、そこで乾いた布で包み、無言で上からゴシゴシと拭きました。
そしてもう一枚乾いた布を持ってくると、それをマトの肩からかけ、暖かい台所の火のそばに連れて行きました。
エテラは全く濡れていませんでした。水を弾く魔法を使ったのだわ…マトはぼんやりと思いました。私はたまにしか成功しないけれど…そして、悔しさでマトは涙が止まらないのでした。
マトは身体が乾くと、エテラが淹れてくれたお茶を断って部屋へ向かいました。
嵐が静まって静かな雨になってきたので、エテラは他の客たちが帰り始めるのを、順番に見送りをしました。
ほとんどの食堂のお客はこの村に住んでいる人たちだったので、家路につくことができたのでした。
宿泊している客は半分以上がブラーフの森へ向かう道を行く人たちでした。あちら側の橋は流されずに持ちこたえていましたが、川の水が橋に届くまで水位が上がって危険だったので、皆もう少し落ち着くまで宿にいるようでした。
それから3日間、雨は降り続きました。橋の修復は絶望的だということでした。水量が多く、川岸をどんどん削って流していました。マトはとても食事が喉を通らないし、心配で寝ることもできませんでした。
コマドリはエテラに言って、柔らかいタオルと水に溶かした麦の粉を用意してもらい、くちばしにつけたりしているうちに、少しずつ瞬きをするようになってきました。
「マトさんも少しは食べてほしいのだけど。」
エテラはマトやコマドリを気遣いながらも、声をかけることはありませんでした。雨の中、毎日川まで様子を見に行くマトに付き添い、そして無言で宿に帰るのでした。
「橋が出来上がるのは半年後だそうだよ。」
嵐がおさまった朝にやってきた若者が、村のニュースを持って毎朝顔を出しました。若者は、おばあさんに薬を届けるのは諦めたと言いました。
「魔法使いに手伝ってもらっても橋の完成には半年はかかるらしいよ。半年もうちのばあさん待てないだろうから、雨がやんだら、誰か魔法使いに頼んで運んでもらうんだ。」
箒で飛べる魔法使いは、こういう時に有難い存在でした。
そして、やっと太陽が顔を出した日、マトは朝早く宿代を払い終えると宿の外に立てかけてあった箒を持って川へ向かいました。コマドリはすっかり元気になり、マトはどこか好きなところへ飛んでいけばいいわよと、コマドリを外へ放しました。
「元気になってよかったわね、あんたみたいに私も飛べたらいいのだけど。」
心配そうにマトを目で追うエテラを見て、宿の主人が言いました。「エテラ、途中まで見に行ってやりな。」
マトは震える手で箒の肢を掴んでいました。マトは箒が嫌いでした。昔はどんなにか飛ぶ練習をしたことでしょう。自分の背丈ほどの木を飛び越えるくらいが精一杯で、箒は一度もマトを乗せて空高く飛んではくれませんでした。この箒は、おばあさまがマトのために特別に作ってくれた大切な箒でした。でも、何年か練習してどうしても乗れないことがわかると、マトは箒を納屋にしまいこみ、一生見るまいと思ったのです。そして、今、イレーンの魔法の会で魔法使いはやめようと思ったマトの心を、今一層この箒が傷つけるのです。
それでも、もうこの箒しか頼れるものはありませんでした。キトのいる家に帰るには、どうしても川をあと二つ渡らなければならないのです。
マトは箒にまたがって心を落ち着かせました。見ることのできない風を呼び、乗せてもらうのです。
嵐の去った後の、静かなそよ風は、箒で飛ぶにはちょうど良い風でした。マトは、風に呼びかけました。私を運んでちょうだい。
しばらくすると、マトは少し浮きました。自分でも驚いたのですが、少し浮いたのです。でもほんの少しでした。膝の高さまで上がったかと思うと、グラグラしてマトはドスンと尻餅をついてしまいました。
それでも諦めずにまた箒にまたがって集中しました。何度も何度もやりました。そして、とうとう飛ぶことができずに、マトは地面に崩れ落ち、泣き始めました。
肩を優しく抱いたのはやはりエテラでした。マトは本当に本当に悲しくて、エテラの胸の中で大きな声で泣きました。そして、もう何年も魔法使いの勉強をしてきているのに、全く魔法が使えないこと、最後の希望だったイレーンの魔法の会で身も心もズタズタに傷ついてもう魔法使いは諦めるつもりだということ、娘や夫のことなど、とめどなく流れる涙とともに、マトはエテラに全てを話しました。エテラは相槌を打ちながら、静かにそれを聞いていました。
「だからね、私どうしても家に帰らないといけないのよ。こんなところで橋ができるまでいつまでも待っていられないの。こうなったら、この川の上流まで行って、歩いて渡るしかないのかしら。」
「マトさん、私が箒の使い方を教えます。」エテラが囁くように言いました。
「私のやり方は学校で教えてくれるやり方と違うかもしれません。でも、ちゃんと乗れるのならこの際なんだっていいじゃないですか。」
マトは驚いて言いました。
「エテラ、あなた自分で箒にまで乗れてしまうの?すごいわ、ええ、なんだっていいわ。私にどうか箒の乗り方を教えてくださいな。」
エテラは自分の箒を持ってきました。
「まずは箒との会話です。箒と信頼関係がなければ飛ぶことは無理ですから。」
「箒と会話?一体箒と何を話したらいいの?」マトはイレーンの魔法の会を思い出していました。木と会話をしろと言われたっけ・・やっぱりここでもそうなのだわ。
「箒も人も同じなんですよ。箒は箒の意思であなたを乗せて運んでくれるのです。呪文をかけたからそれに従っているわけではないんです。それに、箒に乗るには、風の精霊とも会話します。魔法の本に書いてある呪文は古代の風への言葉ですが、今は使われていないので私たちの感情を乗せにくいのです。」
「まあ」
マトは、こんな魔法は初めてだと思いました。
「箒や風の精霊と話をするなんて、妖精みたいだわ。」
「魔法使いの魔法と妖精の魔法を分けて考えなくてもいいと思うのです。魔法の根本は愛ですから。」
「魔法の根本は愛…」
「そう、自分への愛、自分への信頼と、相手を愛したり信頼することは同じです。自分を信頼していなかったら相手を本当に信頼することなんてできません。自分を愛していなかったら、本当の愛が何だかわからないでしょう。
魔法が効かない場合があるのをご存知ですか?それは魔法を受け取る許可を相手が出さない場合です。どれだけ良い魔法であっても、受け取る相手が拒否している場合は効果はほとんどありません。だから、信頼関係がとても大事なんです。自分に対しても同じです。まず自分が自分のことを信頼していなかったら、自分の魔法を受け取ることは難しいのですわ。」
マトは、愛や信頼と言われてカイラーのことを想いました。私は自分を愛していたかしら。信頼は?私は魔法が使えないことで自分を全く信じていないかもしれないわ…だからカイラーのことも信じられなくなったのかしら…マトはまだよく飲み込めないようでした。
「エテラ、私は自分をどうやって信頼したらいいの?私が自分を信頼していなかったら、箒は私に答えてくれないの?」
「そこが面白いところです。箒が信頼してくれるからこそ、自分のことも信頼できるのです。どちらが先ということがないのです。だから、とことん箒と会話をしてください。答えてくれなくとも、箒はちゃんと聞いています。全てのものに意思があるのですから。会話をして、自分を知ってもらう過程で、自分も自分を知ることができます。箒は、マトさんのことを知れば知るほどマトさんのことを大事に思うようになってくれますわ。さっきだって、マトさんが私にご自分のことを正直に話してくださったからこそ、私もマトさんを理解し本当の意味で協力できるのです。」
「そう、まだよくわからないけれど、私はまずあなたを信頼してそれをとにかくやってみるわ。」
マトは箒の肢を持つとそっと撫でました。今までこの肢を持つと不安だけが押し寄せていたけれど、自分からこの箒へ送っていたエネルギーが「不安」だったのだとしたら少し申し訳ない気持ちがしてきました。
「名前のない相手に話すのもやりにくいから、箒に名前をつけてみよう。」
マトは思いつき、「シーナ」という名前が浮かんだのでそれをつけました。
エテラはマトとシーナを二人きりにしてくれました。
「私は店で少し手伝いをしてきます。箒にじゅうぶん話ができたと思ったら私のことを呼んでくださいね。」
「エテラありがとう。」
マトは、川辺でシーナに自分のことを話しました。それこそ、今まで悩んできたことや誰にも話せなかったことなど、心の中にあった色々な感情をシーナに話しているうちに、マトは自分がこんなにも色々考えていたんだということを知りました。そして、悲しかったり寂しかったり、不安だったりしたことを話しているうちに、不思議なことに自分が何に対して恐怖を抱いたり罪悪感を持っていたかなど、自分について客観的にわかってきたのでした。そしてだんだんと心が軽くなり、そしてそんな誰にも言っていない自分の感情を話した相手として、シーナはマトの中で特別な存在となって行きました。たとえ返事がなくても、シーナは聞いてくれているのだわ。そんな風にして、自然とシーナに感謝の気持ちまで湧いてきたのでした。そして、シーナと話している間ずっと、あのコマドリがマトの近くに来て何か鳴きながら行ったり来たりしていました。マトはコマドリも自分の話を聞いているような気がして、コマドリにも名前をつけることにしました。
「あなたの名前はメルね!そうでしょう?」
コマドリはいかにもそうだというようにマトのそばに来て小躍りしました。
「面白い子だわ、メル、あなたにも私の話を聞いてもらいたいわ。」
マトは、昼過ぎまでずっとシーナとメルに話しかけていました。そして、久々にこんな風に楽しくてラクな気持ちになった気がしました。自分のことを全部知ってくれた、このシーナとメルが心の底から大切な友達のような存在になったのでした。メルはマトの頭に止まるようになりました。マトは嬉しくて、久しぶりにニッコリと心から微笑みました。マトがシーナの肢を持って、エテラを呼びに店に戻ろうとした時、向こうからエテラがカゴを持って歩いてきました。
「マトさん、お腹が空きませんか?サンドイッチを作ってきました。一緒に食べましょう。」
マトは急に自分がお腹が空いていることに気がつきました。エテラの作ってきてくれた豆とハーブのパテを使った野菜たっぷりのサンドイッチに、ピンク色のレモネードは最高の昼食になりました。
久しぶりにこんな風にお腹が空いて、美味しいものを食べることができた・・・マトはこの若い魔女エテラに心の底から感謝をしていました。
「それで、私、シーナが返事をしてくれている感じがしてね、」
マトは嬉しそうにシーナとの会話をエテラに話しました。
「シーナはマトさんと話をしたがっているようですね。マトさん、これなら今すぐ飛べますよ。それにしても、そのコマドリは本当にマトさんが好きみたいですね。コマドリは人懐こいけど、こんなに近くまで来るなんて。」
食べ終わると、エテラは自分の箒にまたがって、箒に声をかけました。
「私はいつも箒に風を探して、とお願いしてみるんです。箒は自分が乗れそうな風を探します。強い風でなくても、空気の層があるようなので…」と言っているそばから、エテラは宙に浮き始めました。
そして、浮き始めるとエテラの前方から風が吹いているかのようにエテラの茶色の髪がふわふわと後ろになびきました。そばにあった大きなモミの木のてっぺんまで浮かぶと、エテラは下に戻ってきました。
「まずはここまで、やってみてください。」
「できるかしら…」
「シーナを信じてあげてください。」
「それならできるわ。」
マトはワクワクしながら箒にまたがりました。
「シーナ、あなたの風を探してね」
そう言った途端、シーナはふわっと自然に浮かび上がり、マトは目をまん丸にして喜びました。
「ワーオ!シーナ!嬉しい!私をあのモミの木のてっぺんまで連れて行ってくれる?」
マトがそう言った瞬間、箒はマトを乗せて楽し気に登って行きました。マトはもう嬉しすぎて涙が出てきました。
「シーナ!シーナ!ありがとう!!!」
それから、マトはシーナに乗って前に進んだり、後ろに進んだり、急降下したりスピードを上げたり下げたり、色々な練習をしました。今まで何年も乗れなかった箒に、たった数時間でいとも簡単に乗りこなすことができたのです。
そして、その数時間のうちに、マトは箒にも風にも意思があり、その意思の通りにこちらが合わせると、もっと物事がスムーズにいくということがわかってきました。今までマトは呪文さえ唱えれば、物がいうことを聞いてくれると思っていました。でもそうではなくて、呪文よりもこちらの敬意や信頼が物に伝わり、そしてその愛で物が動いてくれるのです。コマドリのメルは、嬉しそうに鳴きながら空を飛ぶマトについて来ました。最後の方では、メルは箒の肢に捕まって一緒にマトと箒に乗って飛ぶようになりました。
「マトさんは、素晴らしい魔女ですよ。」
はち切れんばかりの笑顔のマトに、エテラも嬉しそうに言いました。
「だって、マトさんは素敵な人だから。物も自然も、マトさんが心を開けばみんな大好きになってくれるんです。どれだけ勉強しても、これは本に書いていないことなんです。でも本当は自分の愛を理解している人ならとても簡単なことだと思います。それに、マトさんは知識がすごいから、これからなんでもできるようになると思いますよ。」
「エテラ!」
マトはエテラに飛びつきました。
「本当に本当にありがとう!ああ、こんなことってあるかしら、昨日までの私はどれだけ雨や風を呪ったかしれないのに!今ではわかるわ、雨も風も、私のために嵐を起こしてくれたんだって!」
エテラは大声で笑いました。
「その通り!」
11.魔法使いの庭
キトは庭に全ての種を蒔き終わり、一息ついていました。
風は爽やかな草の香りを乗せて、まるで目に見えるように渦を巻いて光を土に運んでいるようです。
種は全て、土や種自身にどこがいいか聞きながら蒔きました。最初はよくわからなかったけど、キトは火の精霊ファルと話す時のように土に話しかけ、時々庭全体を眺めてはなんとなくここだという場所に種を蒔きました。不思議とそのようにして種を蒔くとずっと作業していても疲れることがなく、土と光と風と種が遊んでいるかのように感じられて楽しくて仕方がなかったのでした。
モーラさんにお礼を言いたいわ。食べ物もくださったし、種ももらってしまった。それに、私が寝ている間牛の世話もしてくれていた…
その時、遠くからキトの名前を呼ぶ声が聞こえました。
「ママだ!」そう思って家の門の方を見ましたが、ママは見当たりません。
「キト!こっち!見て!上よ!」
見上げると、ママがいかにも魔女らしく、優雅に箒に乗っているではありませんか。
「ママ!ママ!すごいわ!イレーンの魔法の会で教えてもらえたの?」
キトは興奮して頬をピンクに染め、ぴょんぴょん飛び跳ねながらママを迎えました。
「ふふふ、私の可愛いミニバラさん、ママは今世界で一番ハッピーな魔法使いなのよ。」
ママはふわりと庭に降り立つと、しっかりとキトを抱きしめました。
「ママはお腹がペコペコよ。あなたに早く会いたくて一日中飛んできたの。ああ、早く何もかも話したいわ!
簡単なスコーンとお茶を作って庭で食べないこと?あら?庭が前と全然違うわ、なんだか、なんだか
そうね、前よりも庭が生きている感じがするわ!」
二人は、無事に再会できたことを心の底から喜び合いました。
「あら、ママ、このコマドリはなあに?ママの頭の上に乗ってるわよ。」
「立派な魔法使いのところに来てくれた、コマドリのメルちゃんよ!」
ママは美しい瞳をウインクさせて言いました。
「ああ、ママ!なんて素敵なの!」
ママは台所でテキパキとスコーンを作りました。キトは熱いお茶を入れて、濃いクリームに砂糖を入れて泡立てました。そして庭に出てお互いにこの数日体験したことを話し始めた時でした。
「あたしもあんたたちの話に入れとくれ」
「モーラさん!」
キトを助けてくれた妖精のおばあさんが、家の門のところに立っていました。
「会いたかったんです、私お礼を言えてなくて…」
キトが近づいていくにつれ、おばあさんはよく見ると背の高い赤い髪の綺麗な男の人になっていました。
「パパ!」
「カイラー!」
「ははは、りんごちゃん、僕がわからなかったの?妖精のモーラさん、うまくできただろう?」
それから3人はスコーンを食べながら美しい香りで満ちた幸せの庭でお互いの話を聞いたり話したり、これ以上ないくらいの幸せを感じながら過ごしました。モーラさんのスープも蜂蜜入りミルクも、パパの得意な料理なのにキトはなぜ気がつかなかったのかしらと思いました。こんなに幸せな気持ちを味わえるのも、また、火や水や、風や土のおかげなのかもしれません。
ママは立派な魔法使いになりました。コマドリのメルもママの手伝いをするようになりました。そして、キトも魔法使いになることにしました。パパはどっちでもキトが好きな方でいいと言ったけれど、ママは一緒に魔法を使えることができるととても喜んでくれました。
そして、ママの庭はこの村で一番美しい庭になりました。どの植物も輝いて元気で、いつでも話しかけてくれました。こちらがたくさん話しかけさえすれば、みんな答えてくれるのです。魔法使いの庭とは、そういう庭なのです。
おしまい












